伊勢崎操車場
滞貨を捌け!
表紙へ









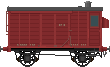

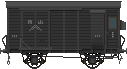
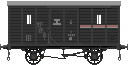
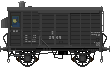
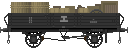
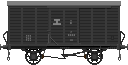
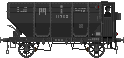
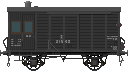

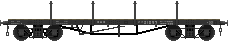


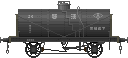
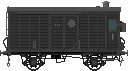
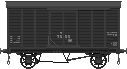
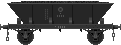
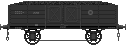
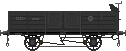
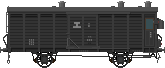
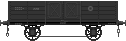
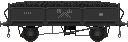

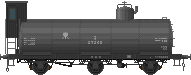
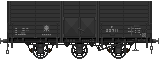

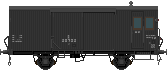

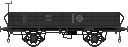
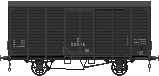

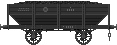
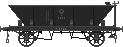
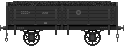

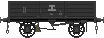
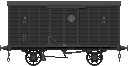



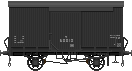
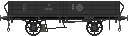
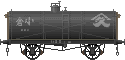
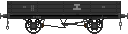
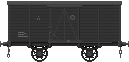
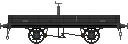
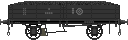
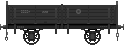
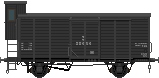
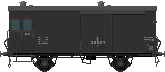
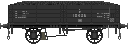
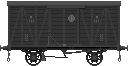
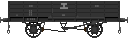
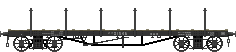
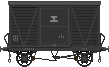
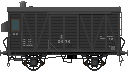


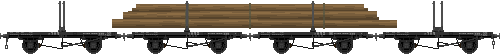
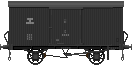
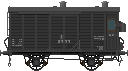
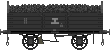
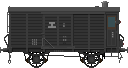
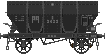
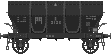

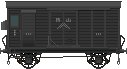
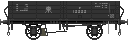
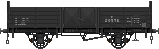
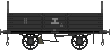
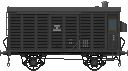

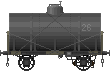
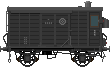
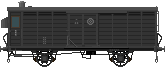
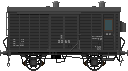
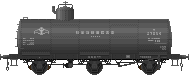




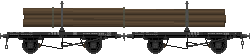
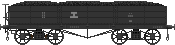
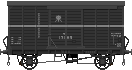

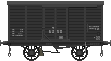
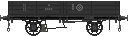


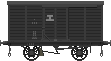
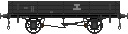


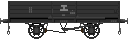
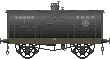
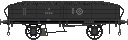
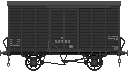
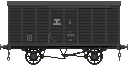

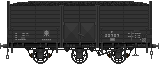
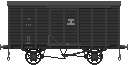
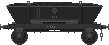
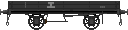
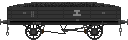
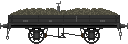
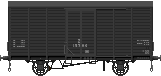
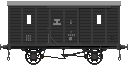

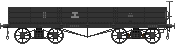
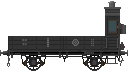
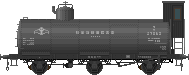
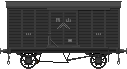
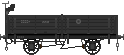
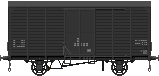
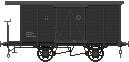
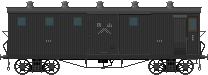
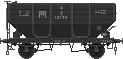
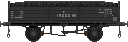
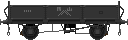

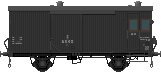
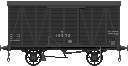
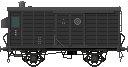
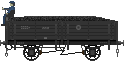

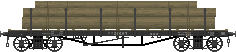
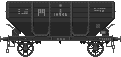
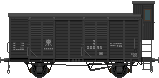
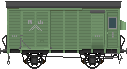

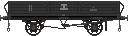
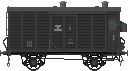

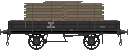
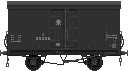
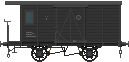
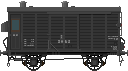
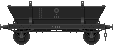
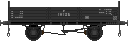
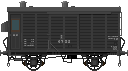
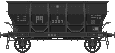
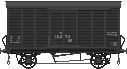
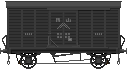
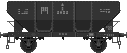
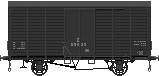
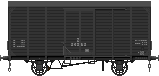
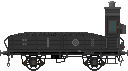

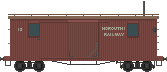
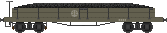

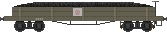
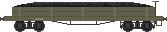

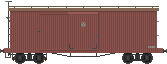
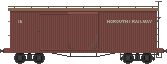
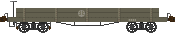
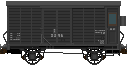

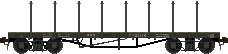
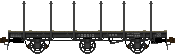
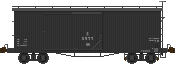
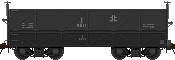
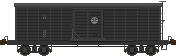
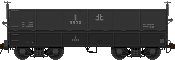
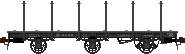
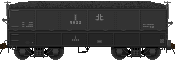


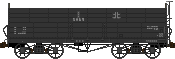

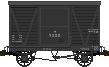
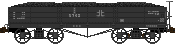
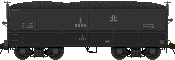
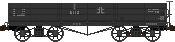
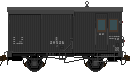
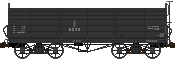

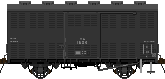
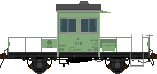
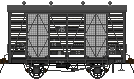
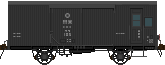
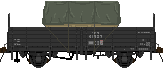
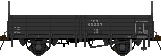

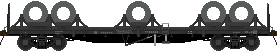



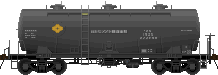
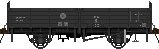
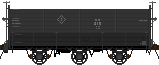
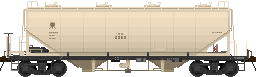

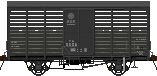
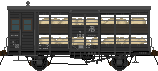

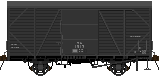
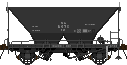
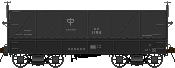
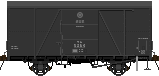



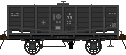
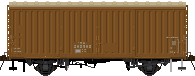
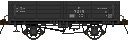
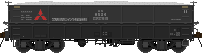
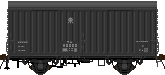
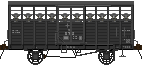
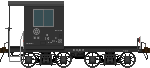

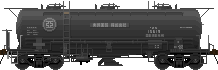
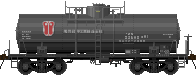
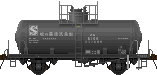
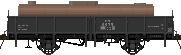
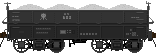

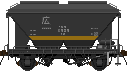
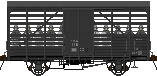

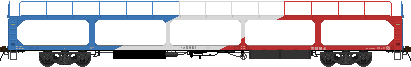
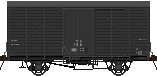
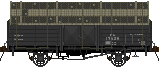

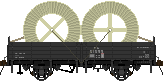
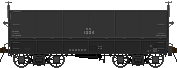
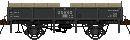
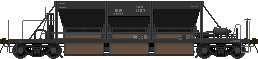
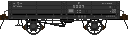
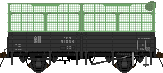


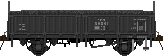
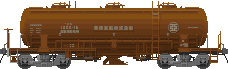
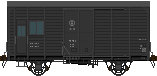


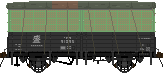

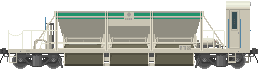
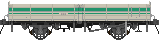
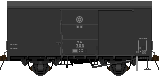
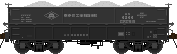



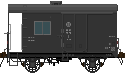
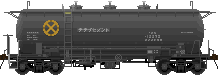
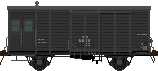
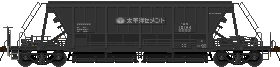
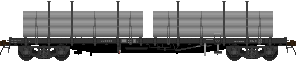



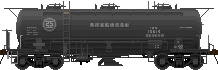

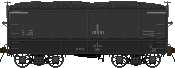


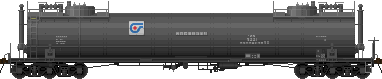
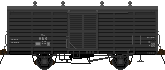
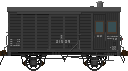
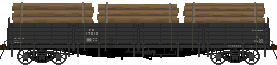
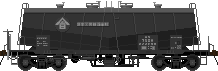


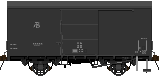

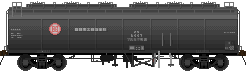
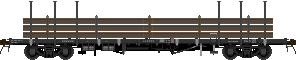
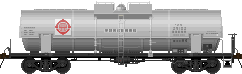
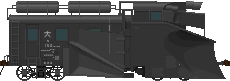

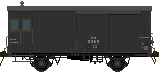
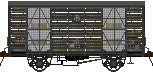

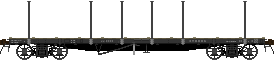
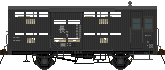

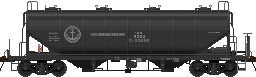
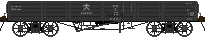
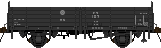
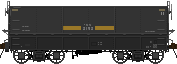
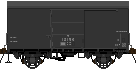
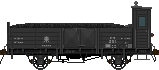
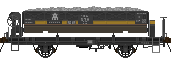

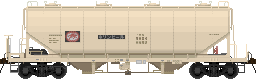
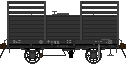
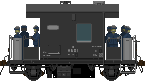

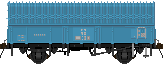
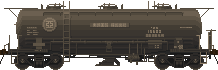

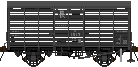
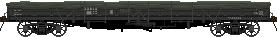

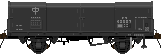

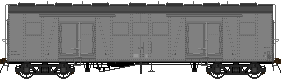

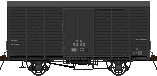
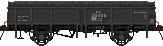
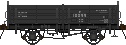
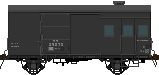

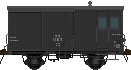

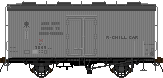
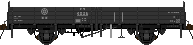
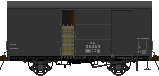
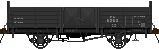
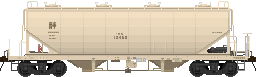
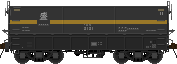
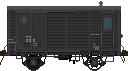

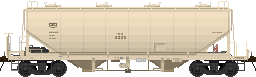

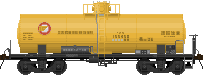
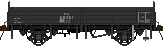
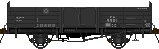
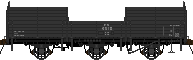
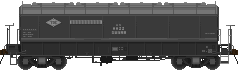

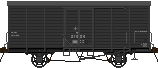
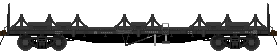
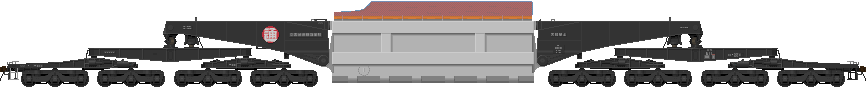
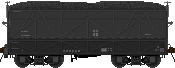

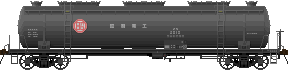
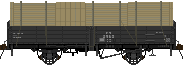
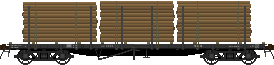
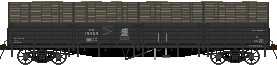
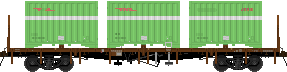
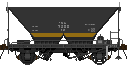
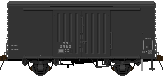
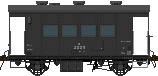

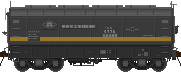

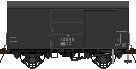
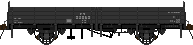
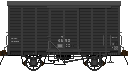
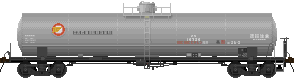
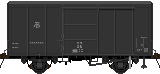
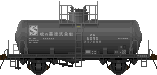

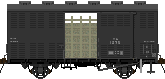
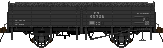



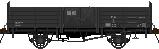
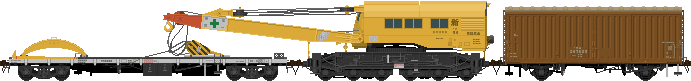
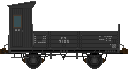
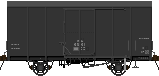
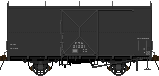


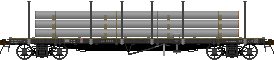

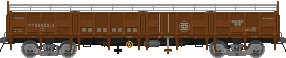
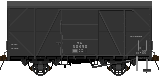
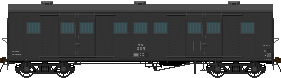
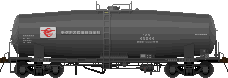

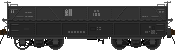

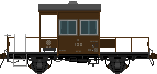
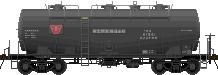
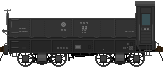
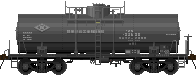


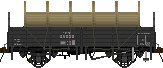
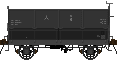

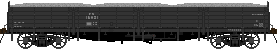
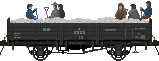


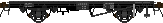
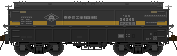

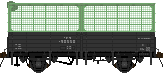
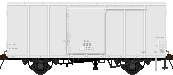
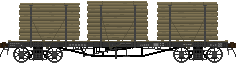

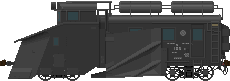
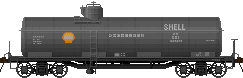
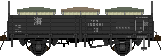
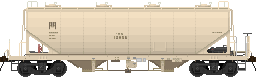

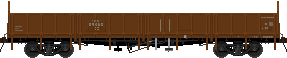

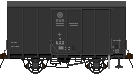



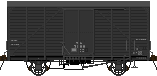
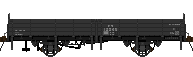
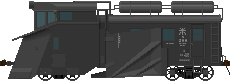
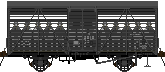

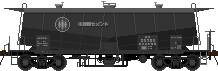
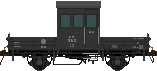
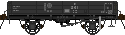
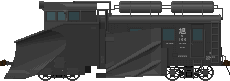
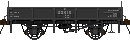
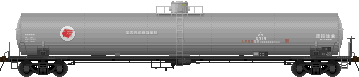
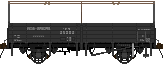

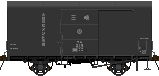
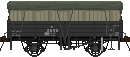
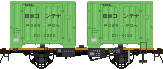

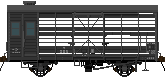
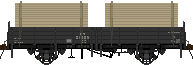
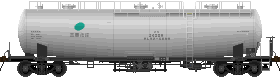
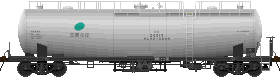

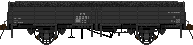

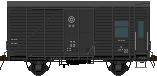
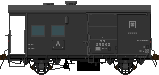

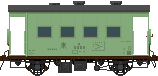
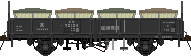
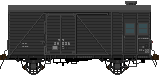
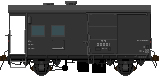
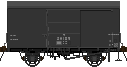

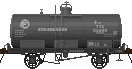
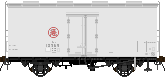
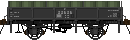

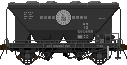
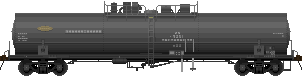

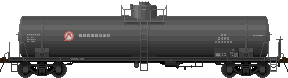
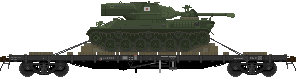

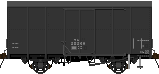


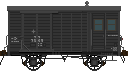
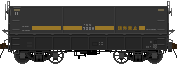
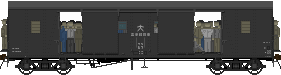
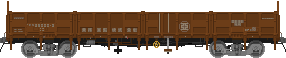


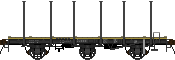
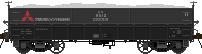

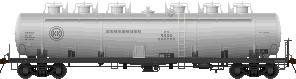
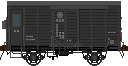
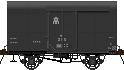
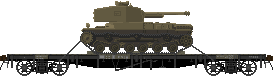
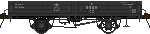
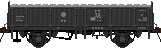
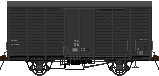

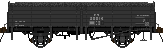
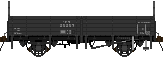
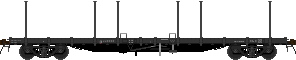
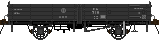
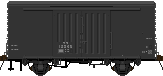
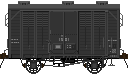
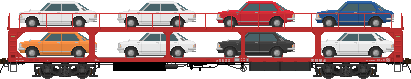


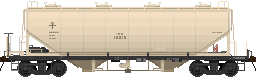

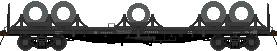
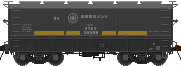
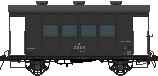
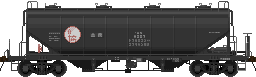
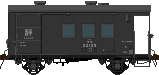
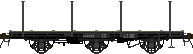
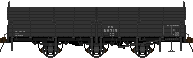
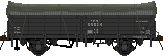
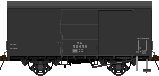
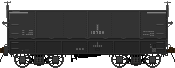
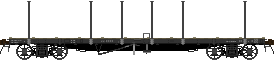
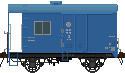
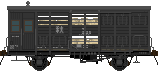
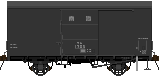
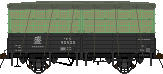
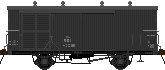
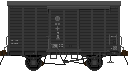
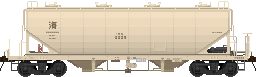
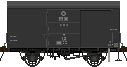


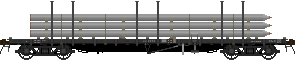
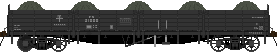
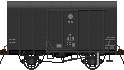
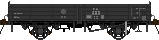
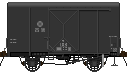

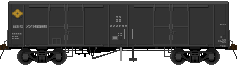

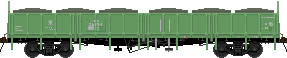
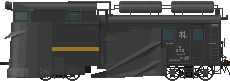

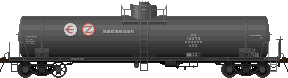
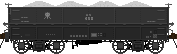
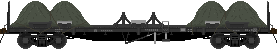
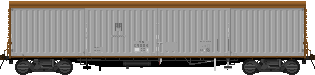

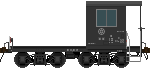
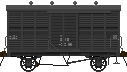
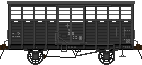

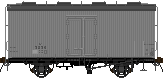
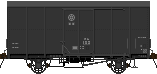
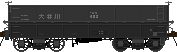
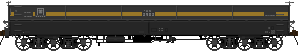

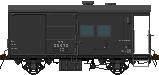

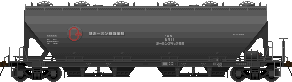
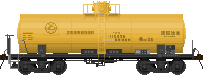
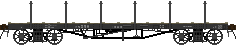
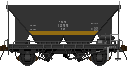
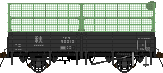

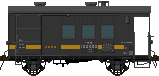
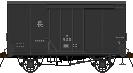

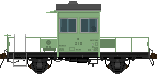
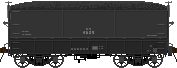
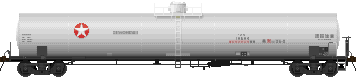
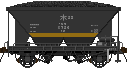
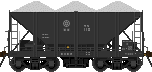
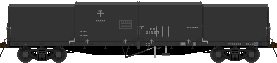
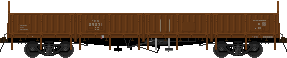

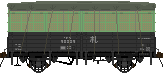

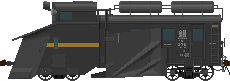

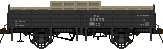
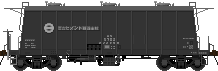
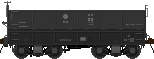
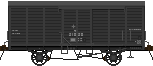

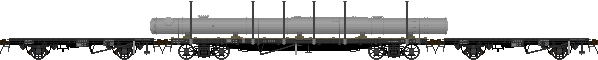
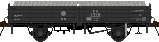
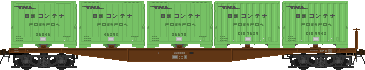



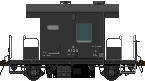
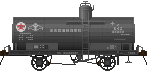
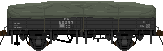
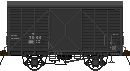

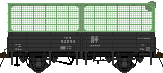


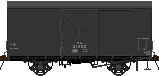
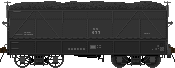


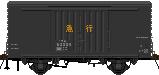
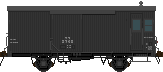
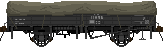

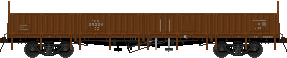
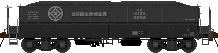
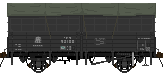

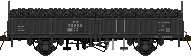
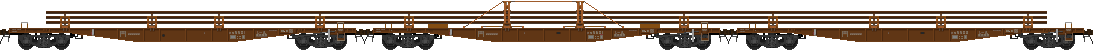
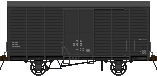
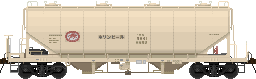
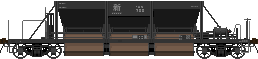
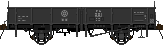


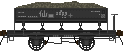

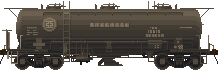
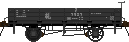
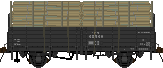
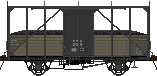
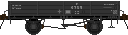

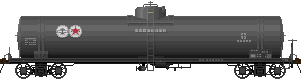
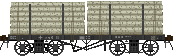
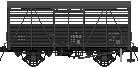
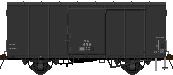
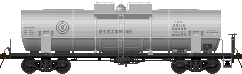
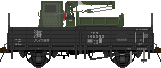
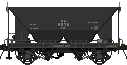

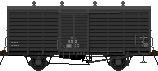
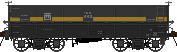
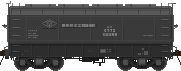
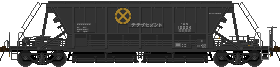
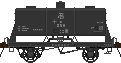
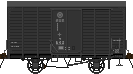
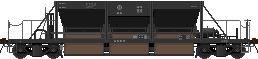



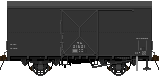

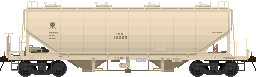
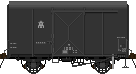
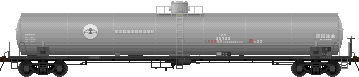
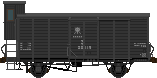
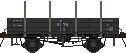
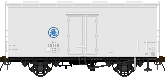

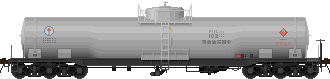

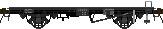
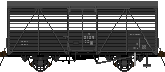

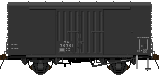

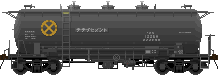

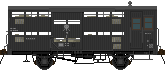
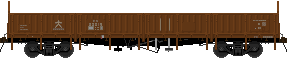
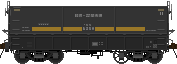
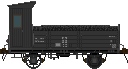
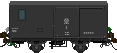
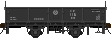
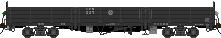
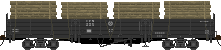

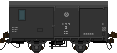
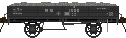
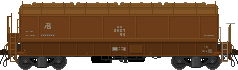

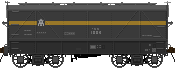
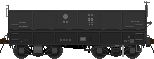
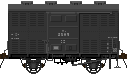

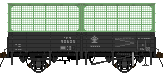
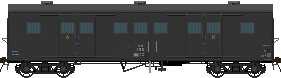
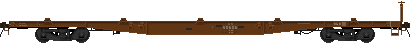
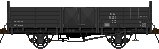
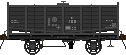



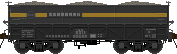
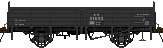

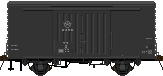
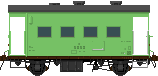
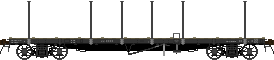
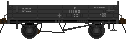


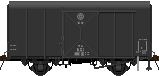

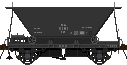
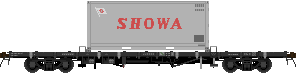


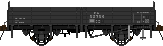

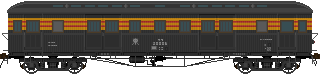




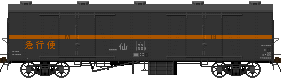

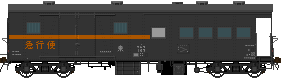


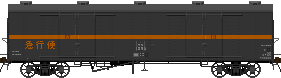





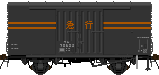

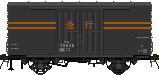






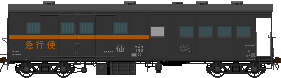


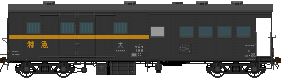


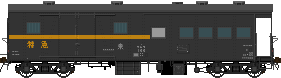
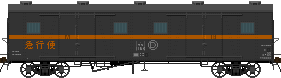


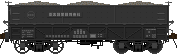
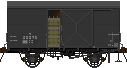

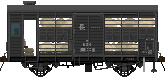
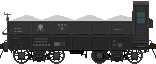
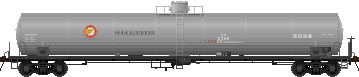
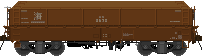
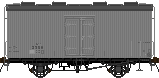
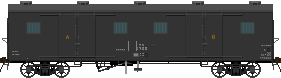

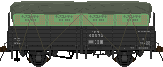
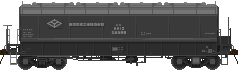
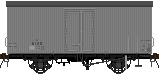
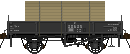
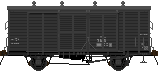
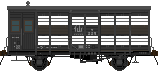
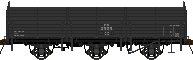


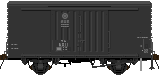

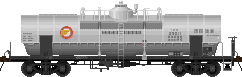
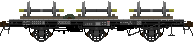
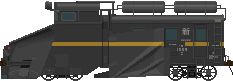
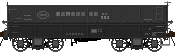
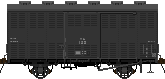

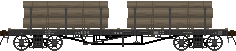
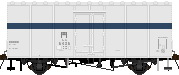
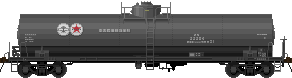
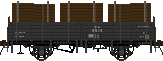
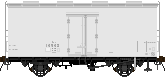
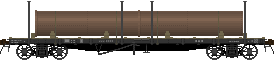
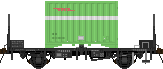
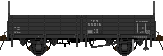
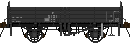
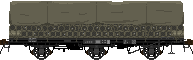
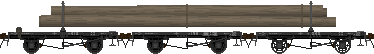
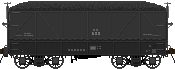

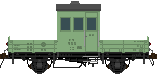

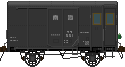
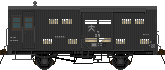

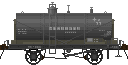


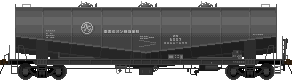

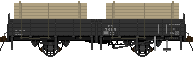
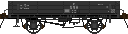
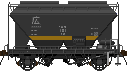
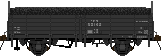
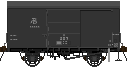

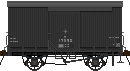
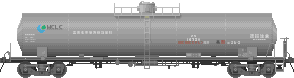
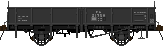

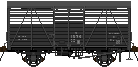

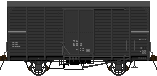


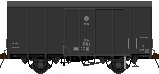
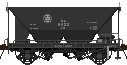
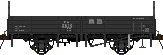
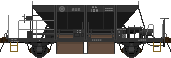

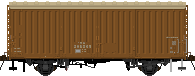

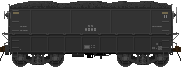
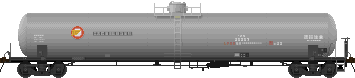
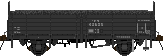

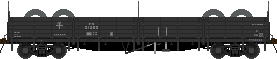
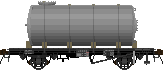
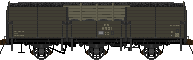

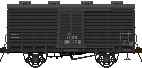
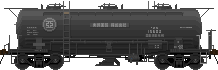

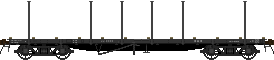
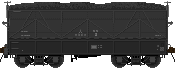
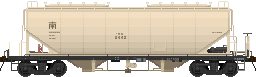




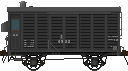
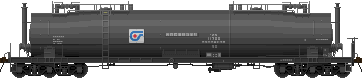





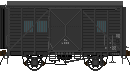


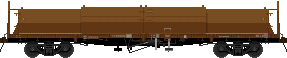
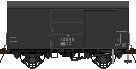
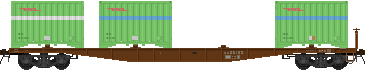

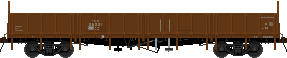
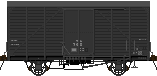
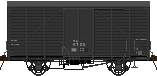
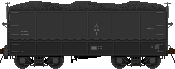
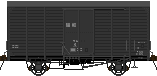
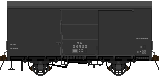
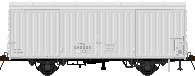
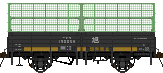
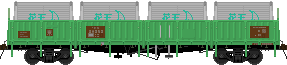
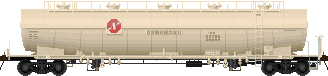


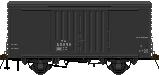

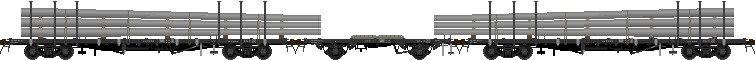

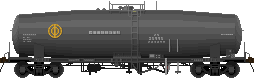



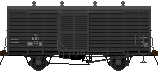
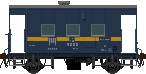
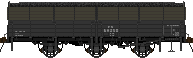
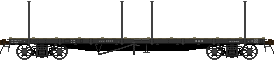
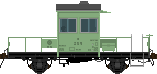
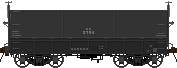

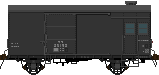


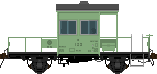
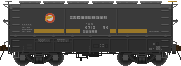


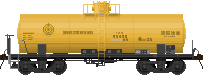
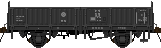
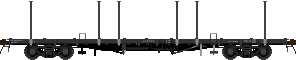
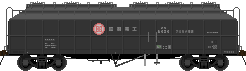

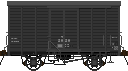
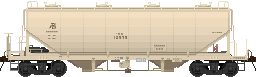
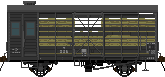

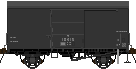

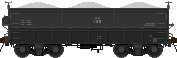
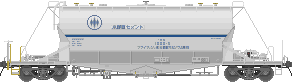

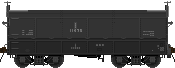
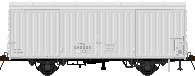
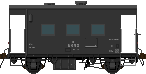
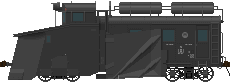
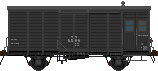
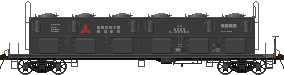

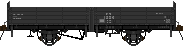

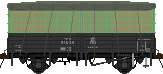


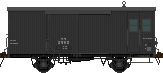
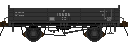
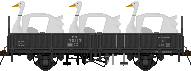
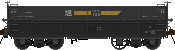
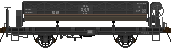
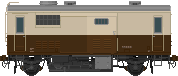
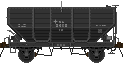
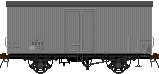

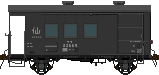
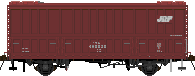
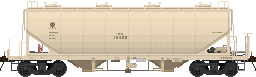

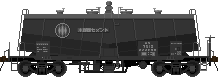
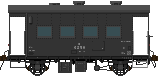
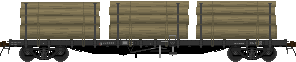
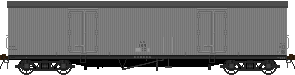

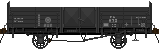


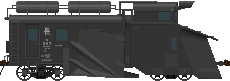


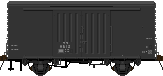
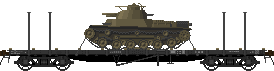
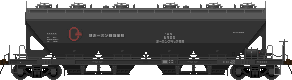
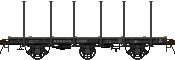
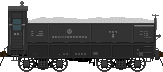
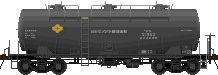
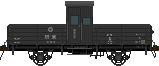


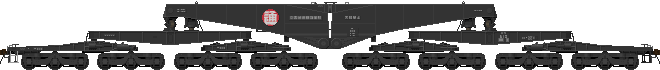
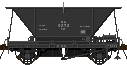
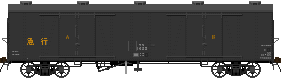
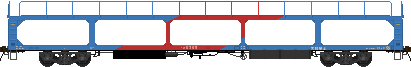
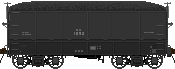

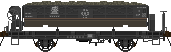
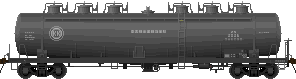


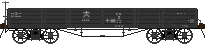



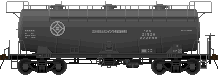



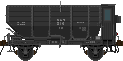

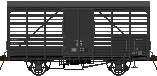
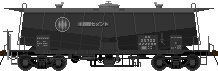
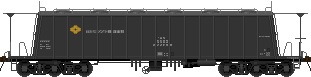
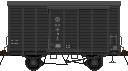
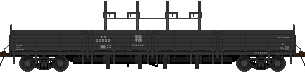
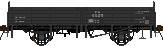
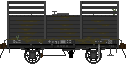
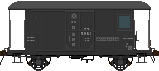


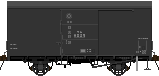
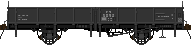

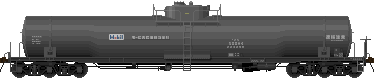

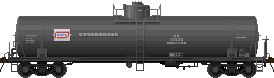
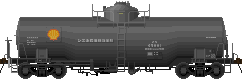
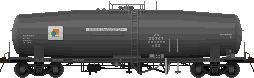
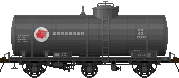
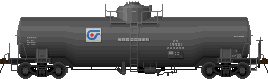
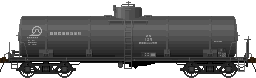

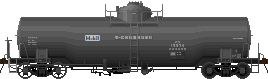
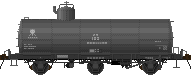
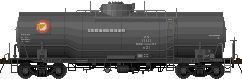
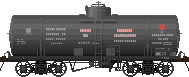
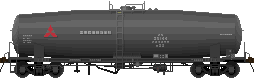
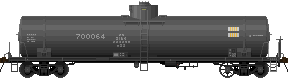
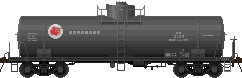
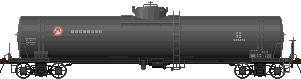
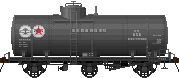
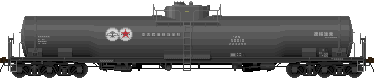
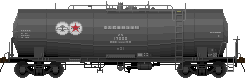
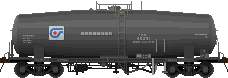

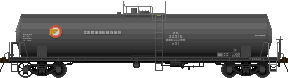
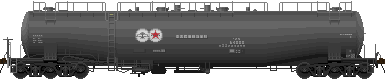


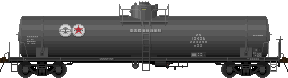
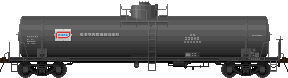
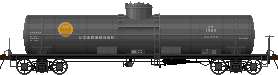
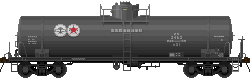
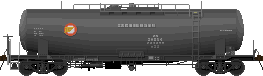
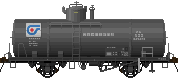
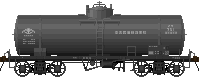
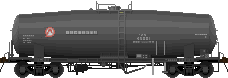
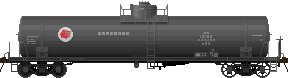

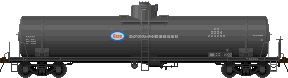

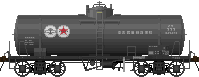
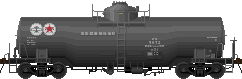
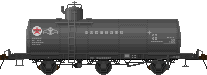
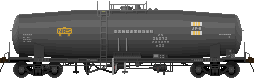
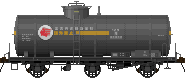
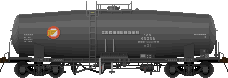
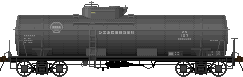
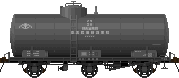

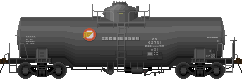
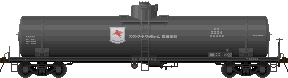
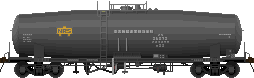
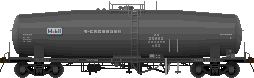
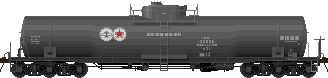
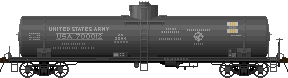
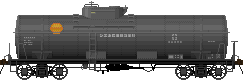
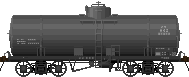
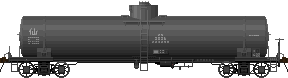
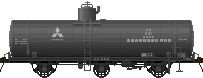
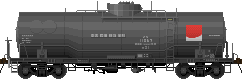
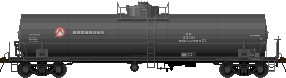

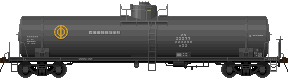
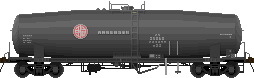
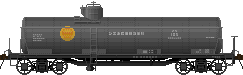
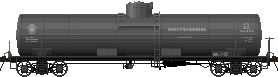
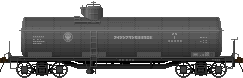
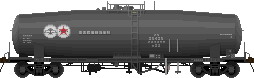
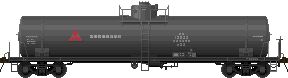

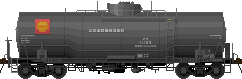

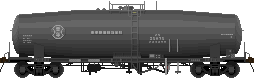
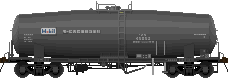
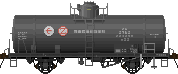
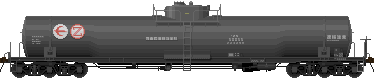
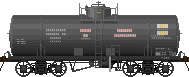
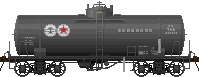
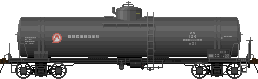
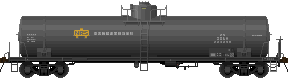
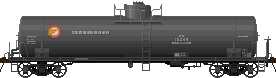
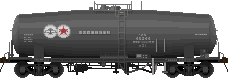
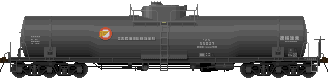
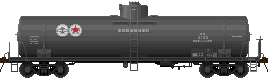
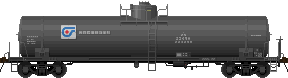
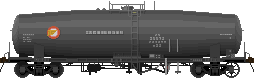
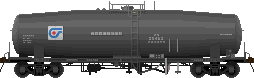
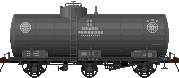
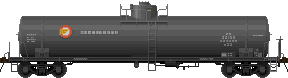
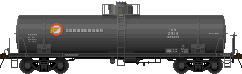
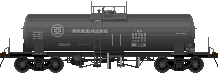
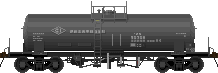
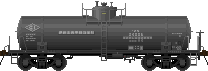
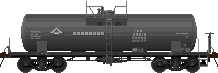
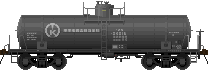

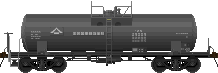
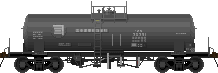
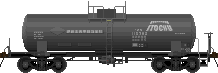
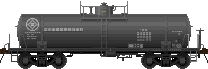
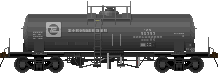
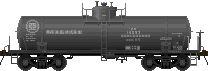
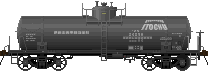
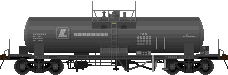
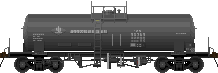
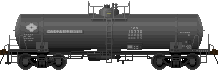
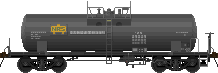
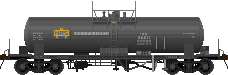
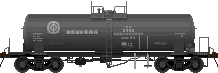
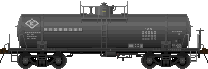
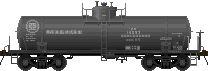
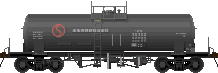
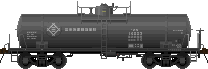
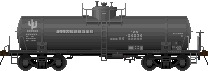
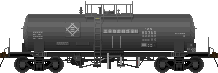
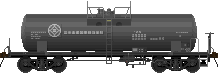
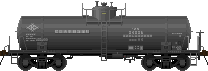
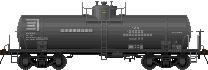
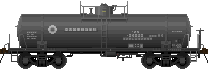
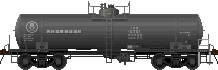
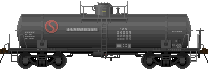
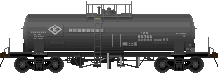
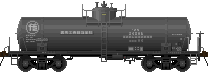
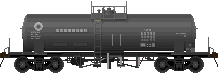
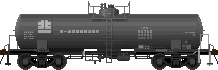
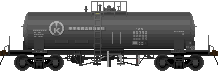
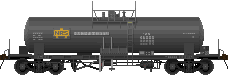
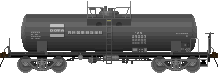
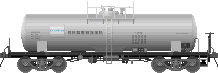
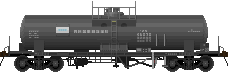
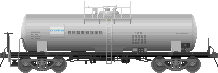

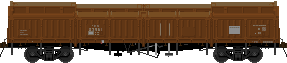

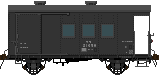

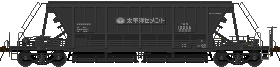
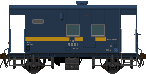

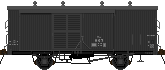
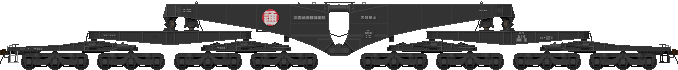
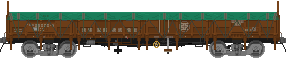
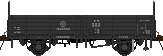
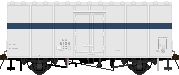
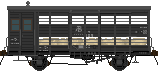
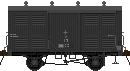

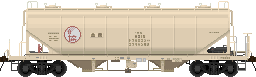
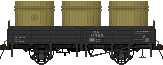
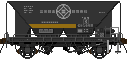
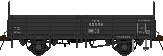
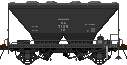
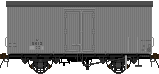
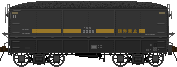
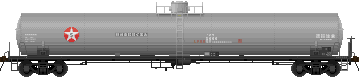
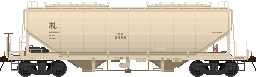
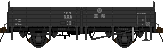
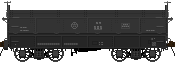
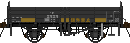
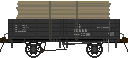

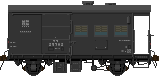
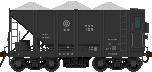
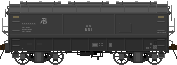
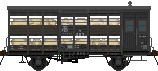
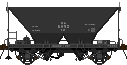


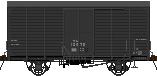
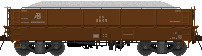

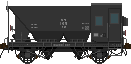
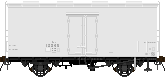
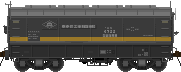

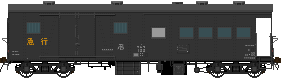
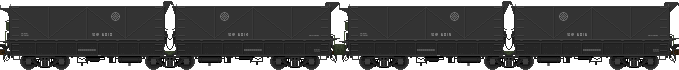


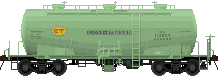

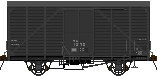
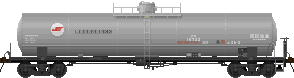
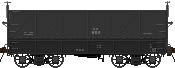
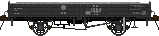
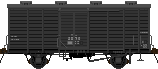


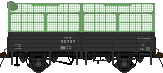

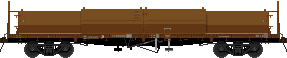
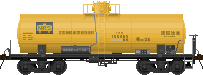
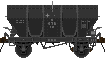
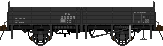
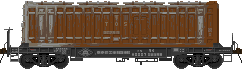
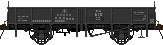
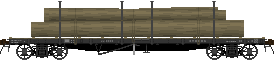
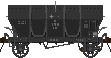
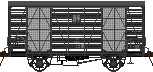
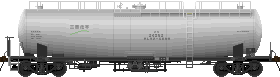
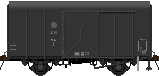
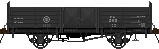
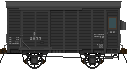
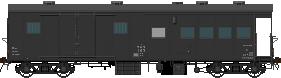

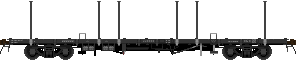
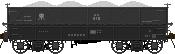
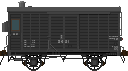
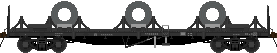
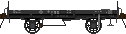
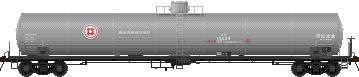


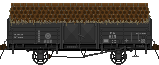
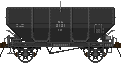


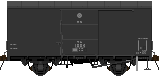

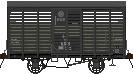
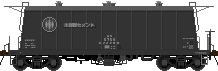

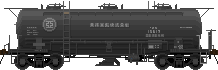
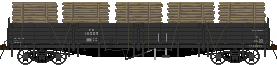
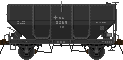
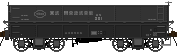

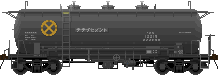
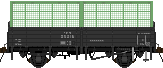
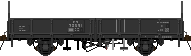




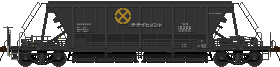
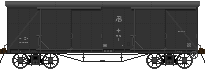

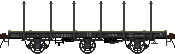
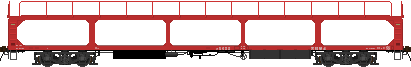
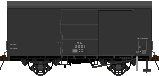
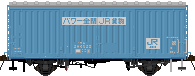

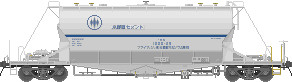
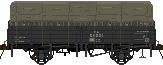
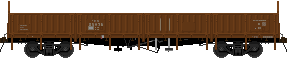
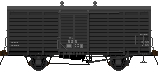





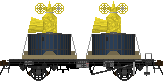

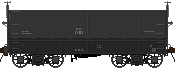

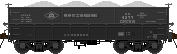
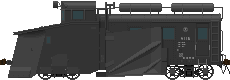
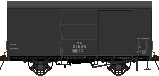
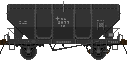
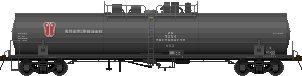

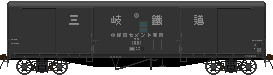


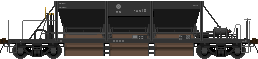
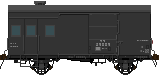
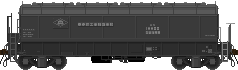
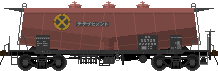
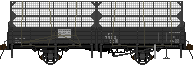
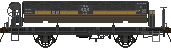
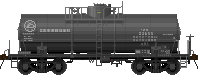

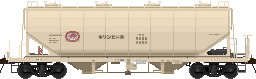
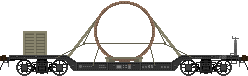

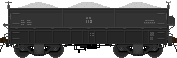
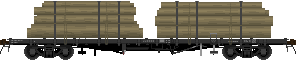
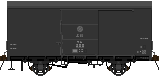
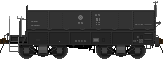
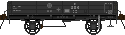
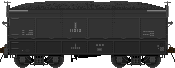
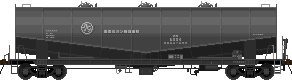
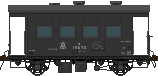
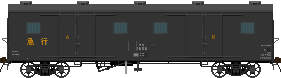

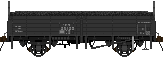
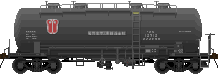
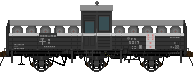
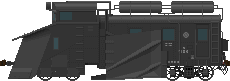
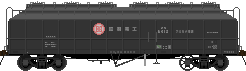

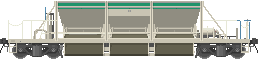

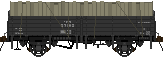
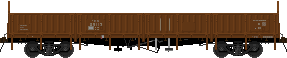


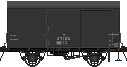
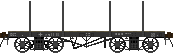
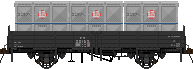


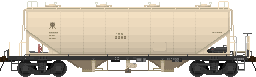
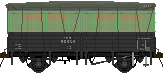

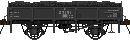

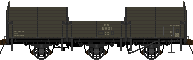



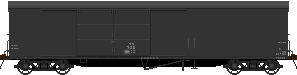
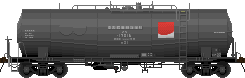


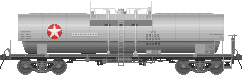
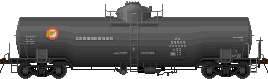
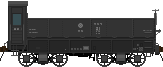
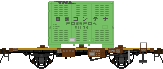
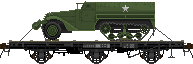
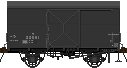


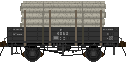

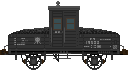


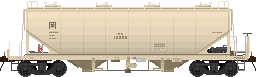
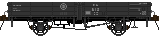
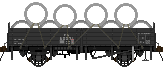
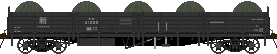
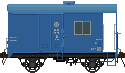

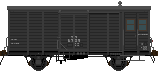
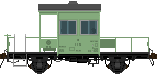
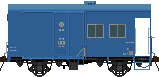

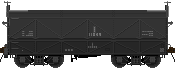
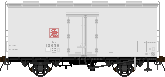
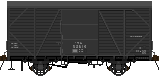


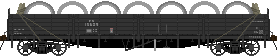
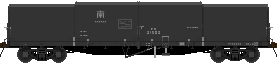
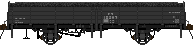

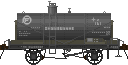
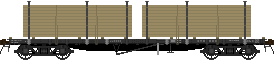
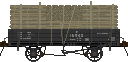
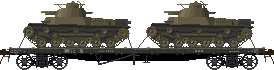
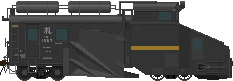

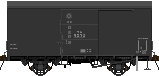




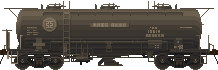


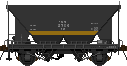

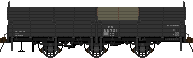
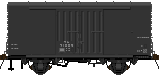
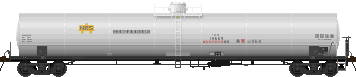
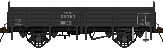

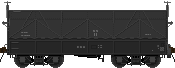

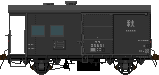
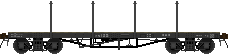

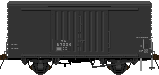

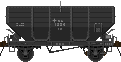
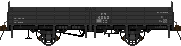





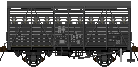

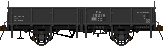



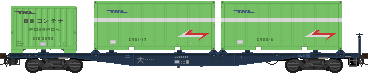

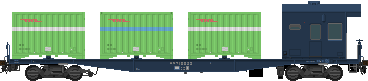
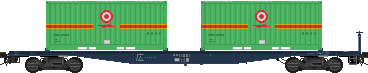
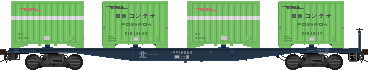











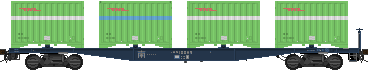


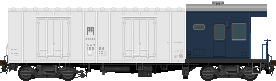



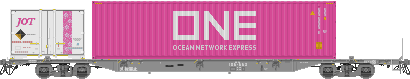

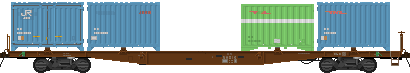
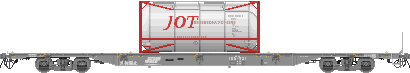
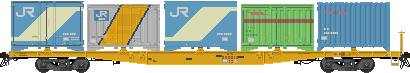
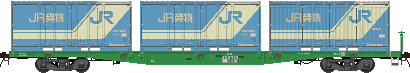
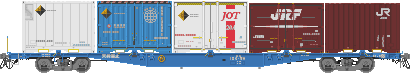


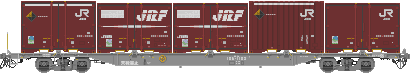
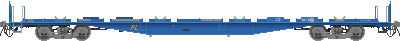
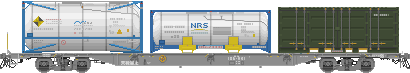

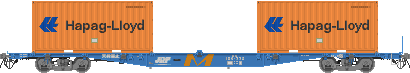

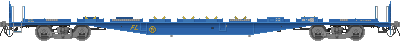
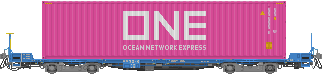
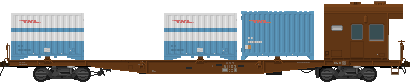
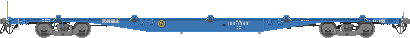
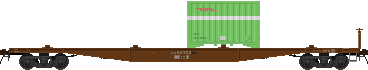
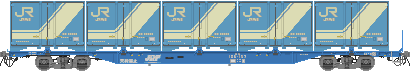
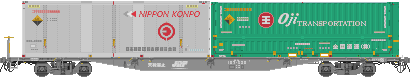
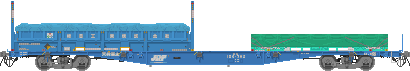
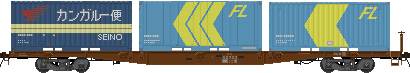
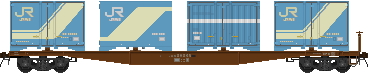
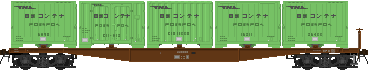
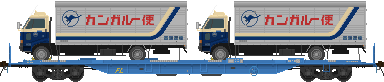
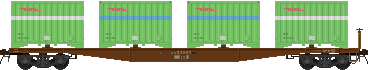
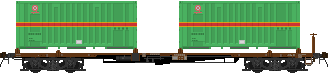
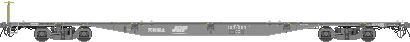
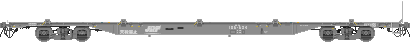



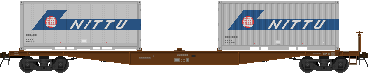
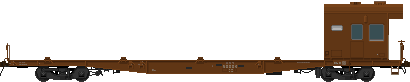
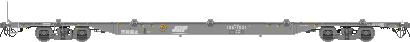

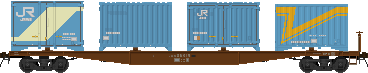
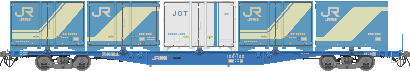




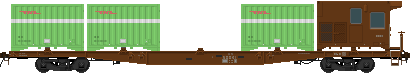

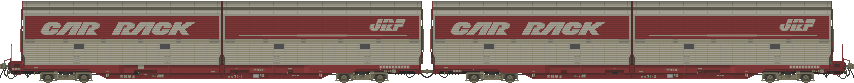
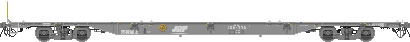
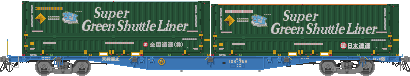

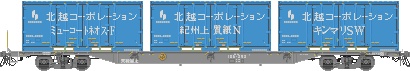
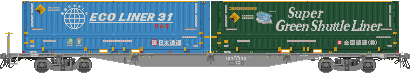
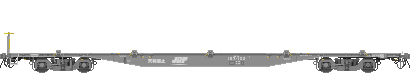

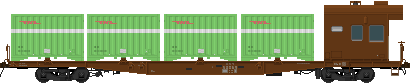
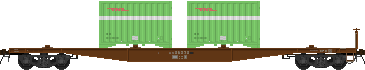
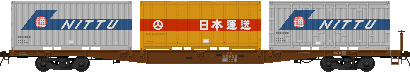


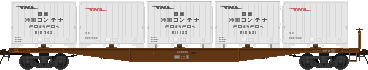
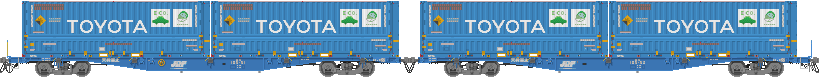
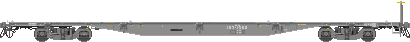
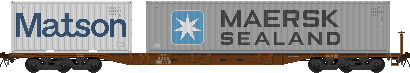

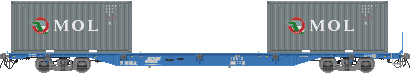
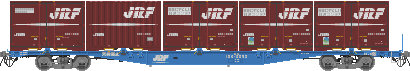
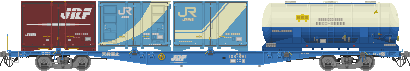

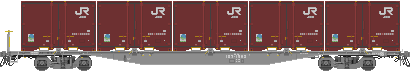
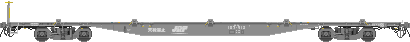
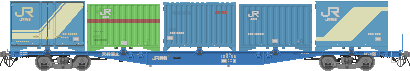

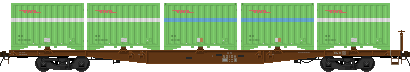
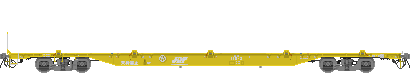
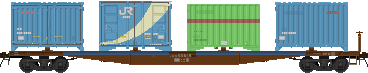
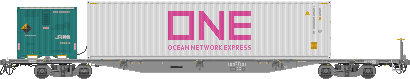
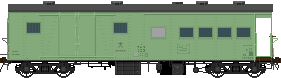


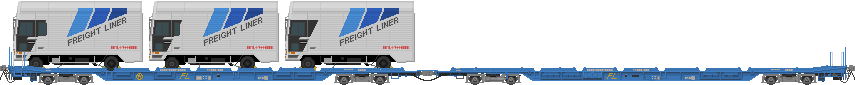
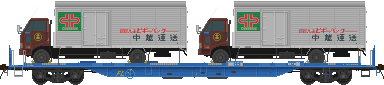
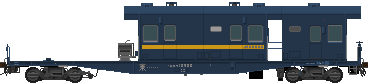



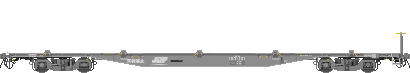
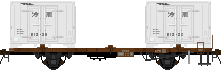
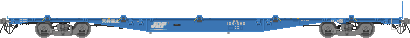
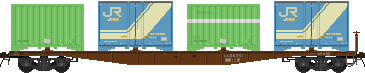
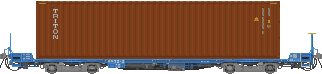


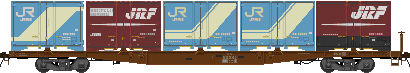
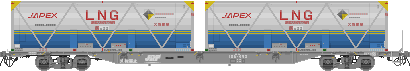

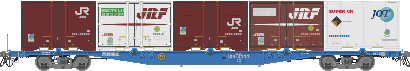
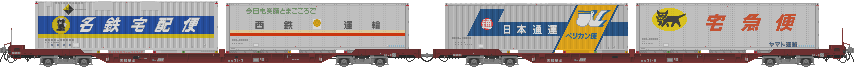
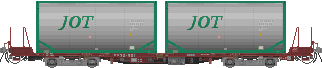

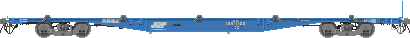

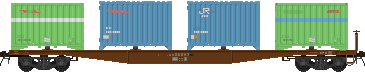
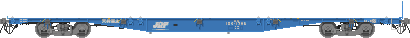
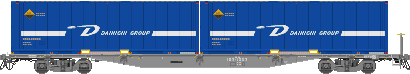

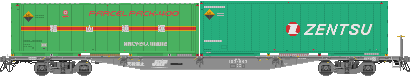
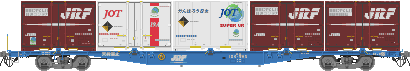
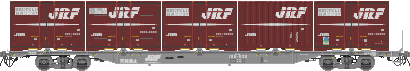

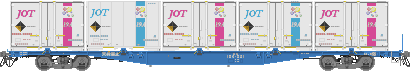
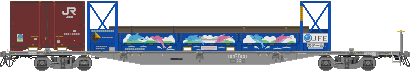
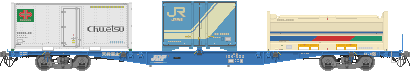
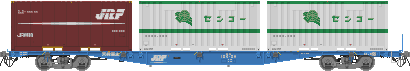

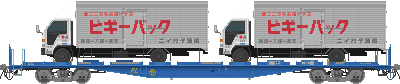
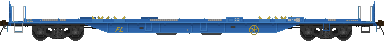
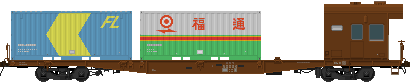
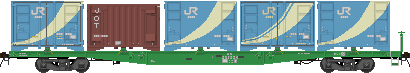
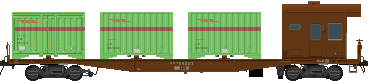


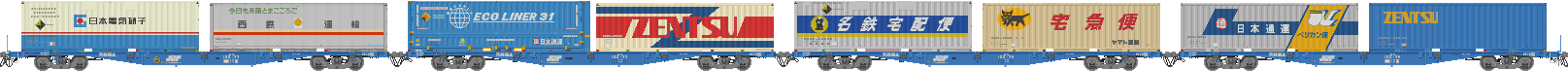
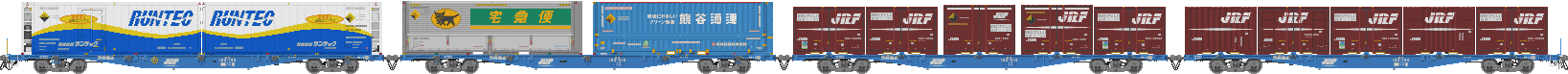
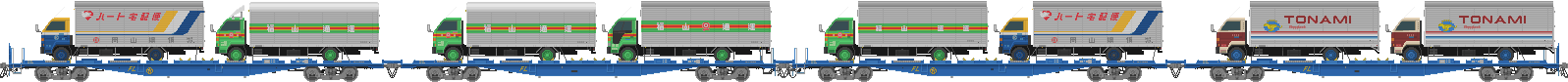
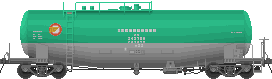
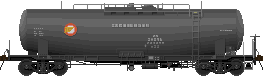
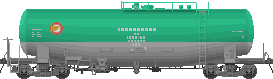
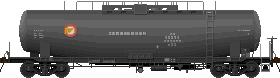
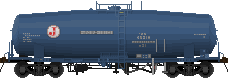
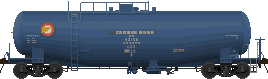
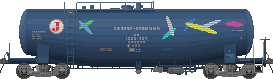
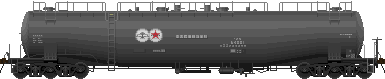
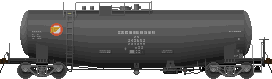
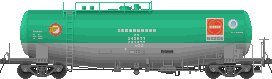
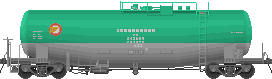
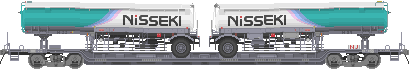
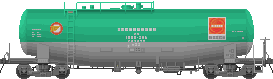
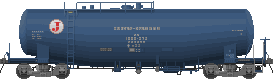
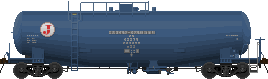
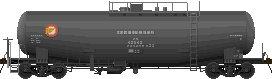
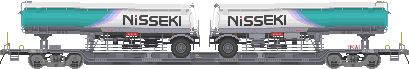
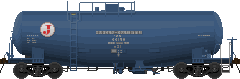
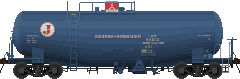

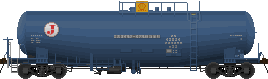
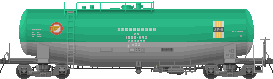

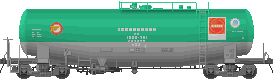
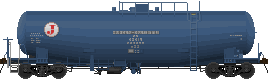

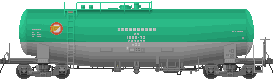
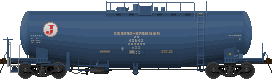
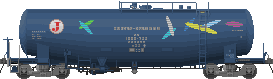
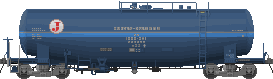
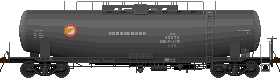
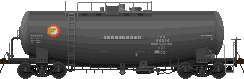
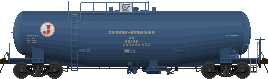
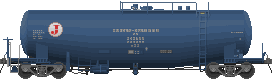
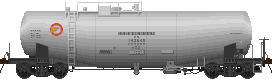
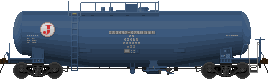
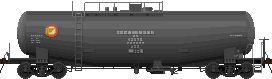
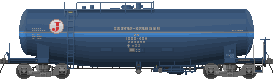
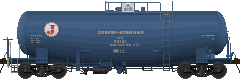
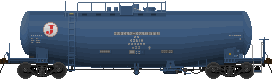
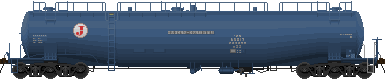
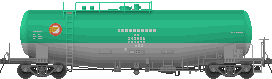
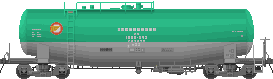
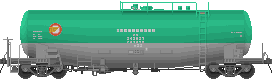
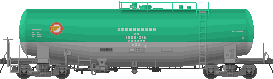


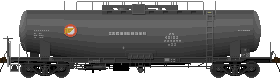

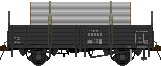

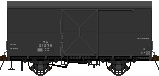
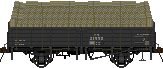
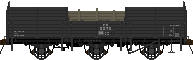
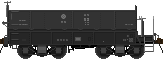
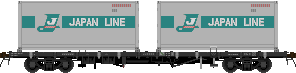
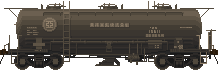
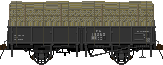
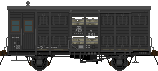
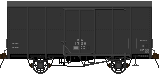
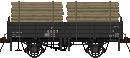
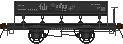


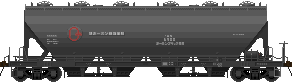
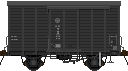
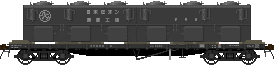
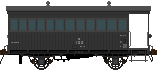
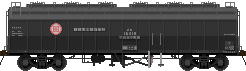
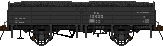
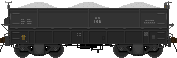
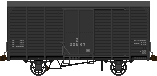
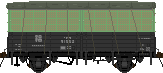
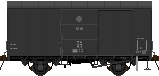
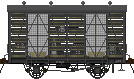
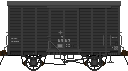


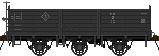

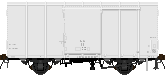

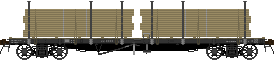
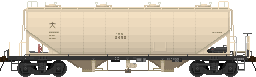
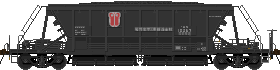
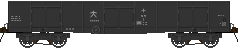
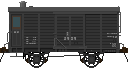
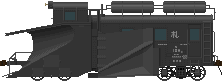
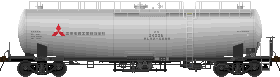
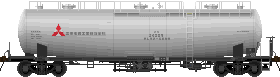
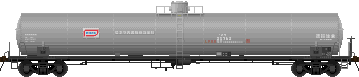
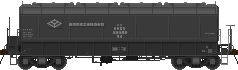
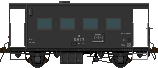
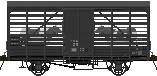

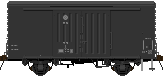





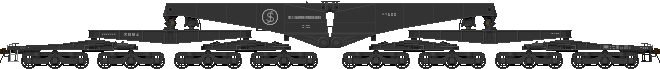

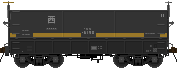

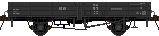



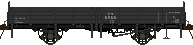



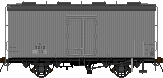
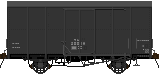

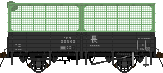

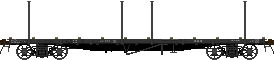

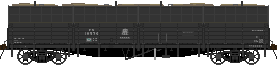
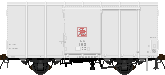

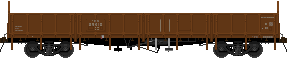
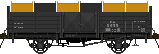

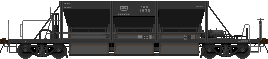
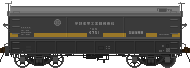
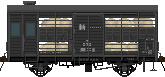
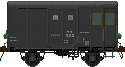
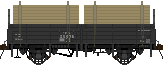



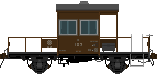
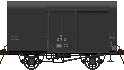
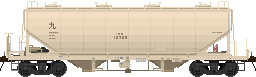

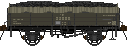
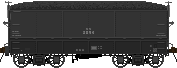
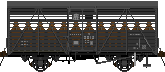
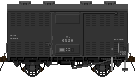


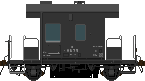
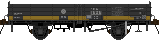
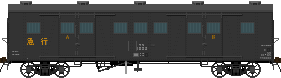


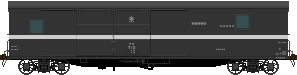
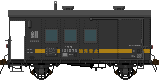
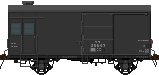
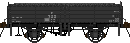
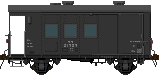

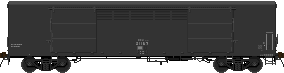
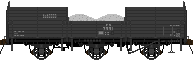
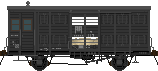

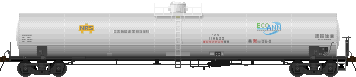
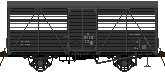

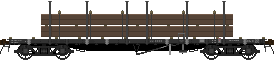
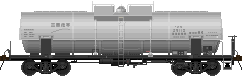

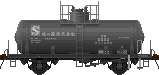


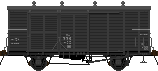
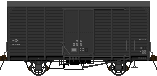
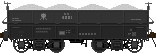
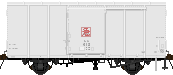
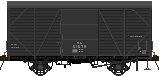
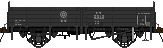
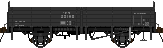
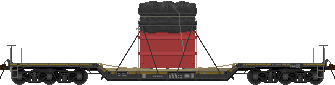
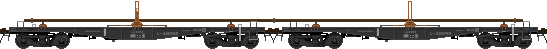
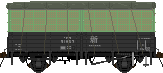
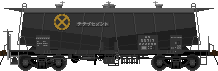
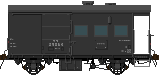
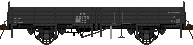

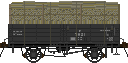
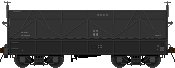

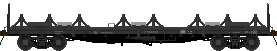
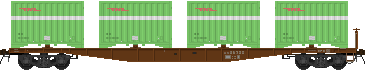
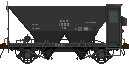
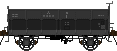
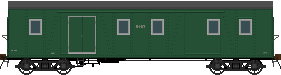
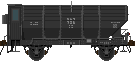
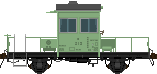
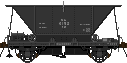
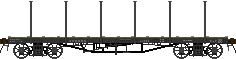
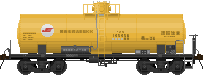


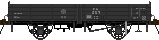

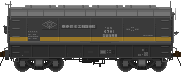
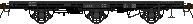

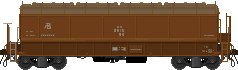

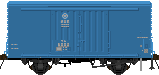
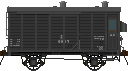
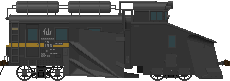
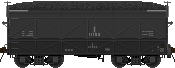
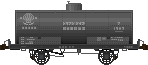
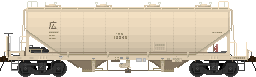


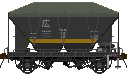
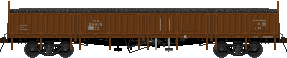
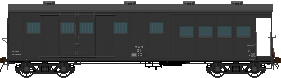

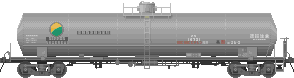
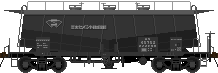

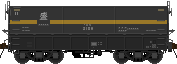

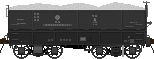

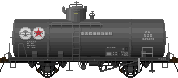
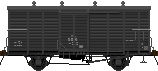
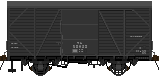

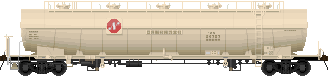
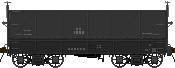

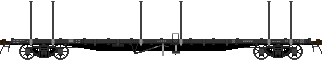
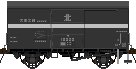
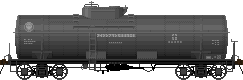
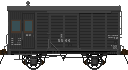
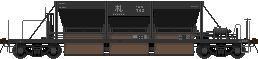
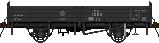

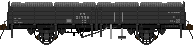
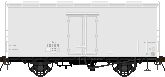
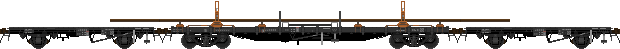
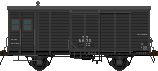

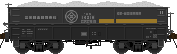
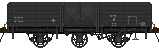
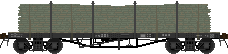
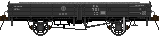
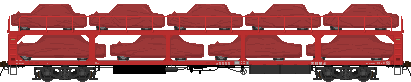
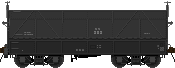
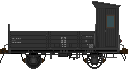
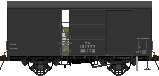
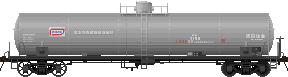
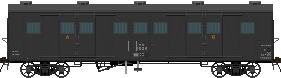

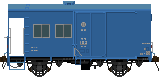
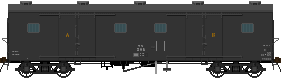

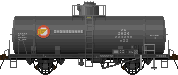




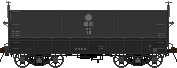
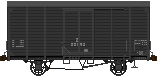
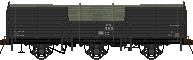
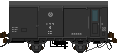


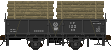

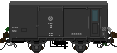

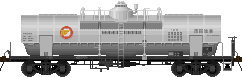
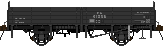
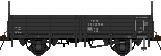


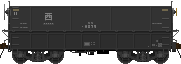
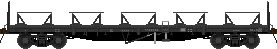
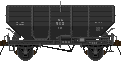


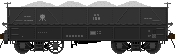


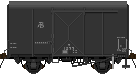
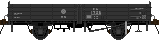

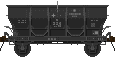
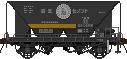

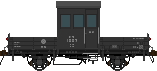
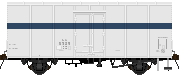
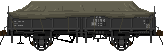

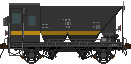
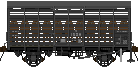
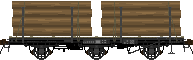
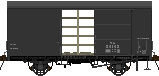

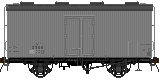
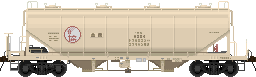
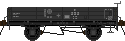
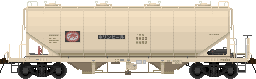

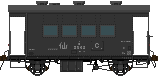
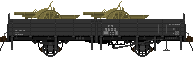
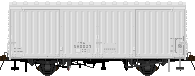
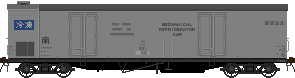
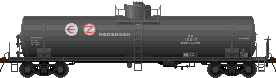

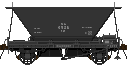
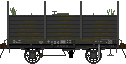
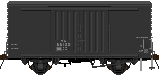

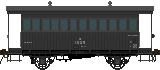
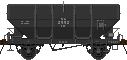
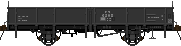


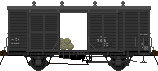

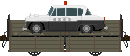

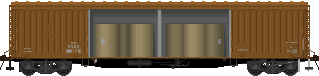

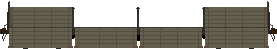
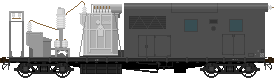


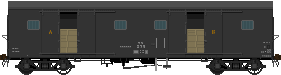
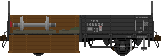
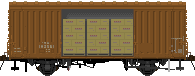
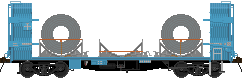
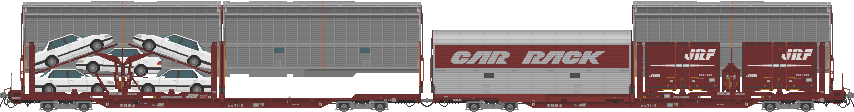
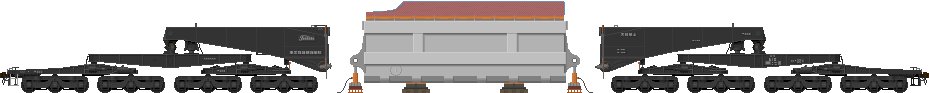
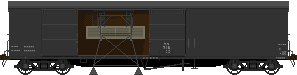

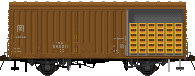
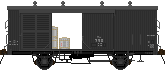

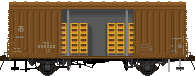
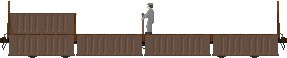
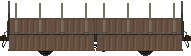



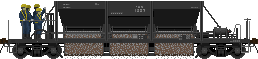

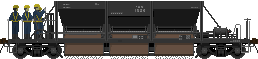

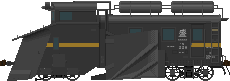
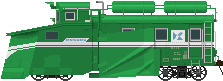
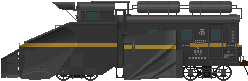
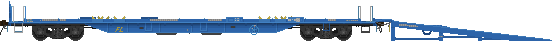
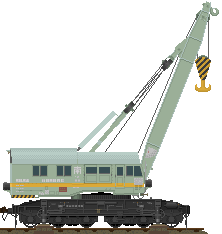
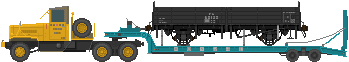
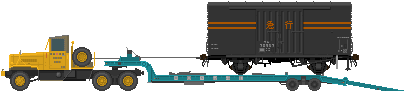
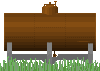
ヤードに思いをはせる。
第二次大戦後、各国の鉄道は、平和の訪れとともに人々の地位向上、モータリゼーションの脅威や石炭→石油への移行と、さまざまな要因により近代化のために努力した。
旅客輸送は 日本の新幹線の成功によって 都市間高速輸送に方向性を見い出し、また列車編成を動力分散化する事により高密度な都市圏輸送を実現した。
貨物輸送は、操車場(ヤード)での時間ロスを無くすためにヤードパスの直行系輸送に力を入れ、トラックや船舶との協同・複合一貫輸送のためコンテナ化が推進された。
また、手間ばかり掛かって収益率の悪い小口貨物や荷物輸送を順次 通運会社の混載貨物に ゆだねていった。
それでも、国民の貨物を積んだ貨車を、最寄りの駅から 先方の最寄りの駅まで任意に送り届ける鉄道の使命を完遂するためには、操車場を経由させて列車間で貨車を継送させる事が不可欠であり、
輸送効率上好ましくないヤードを近代化するために、先進各国の鉄道は腐心し、あえいでいた。
日本の場合は さらに条件が悪く、「側ブレーキを突放貨車の速度制御に使用する。」という間違った方向に進化してしまっていて、触車・転落事故による殉職を多発させていた。
そして、日本の国鉄では昭和59年(1984年)2月にヤード集結輸送の全廃という世界的大英断を下す事になる。
ここでは、国鉄が貨物輸送をなんとか近代化しようと、あれやこれや もがいていた記憶を、徒然なるままに記していこうと思う。
※体系的に貨物近代化のすべてを書くつもりはありません。あまり語られる事の無いネタを中心に、気まぐれに 各項目を追記していきます・・・。
カーリターダ
操車場の近代化・安全化においてまず考案されたのが、突放や散転された貨車を適宜減速する地上装置である。これをカーリターダーと言う。
今までは「乗込制動」と言って、転がってくる貨車に制動手・連結手が貨車に飛び乗ってブレーキを掛けており、動いている車両の直前横断や転落は当たり前の危険な作業をこなしていた。
カーリターダーは戦前にドイツや米国で考案され、日本でも昭和12年(1937年)に新鶴見操車場に試験導入された。ただこれは戦災で廃止。
その後、戦後すぐの昭和24年(1949年)に米国から再輸入されて新鶴見操車場に設置された。
これは空気圧で動くブレーキシューで貨車の車輪を挟んで減速するもで、ハンプ(坂阜)から散転されてくる貨車を捕らえるのを目的としたもの。
ただ、元々が連結器緩衝器の容量の大きな重量級車両用に開発されたシステムなので、当初は使い物にならず、日本式に改良するのに苦労したようだ。
日本ではこの方式のカーリターダを「空圧式カーリターダ」と呼ぶ。以降、各地のハンプヤードに導入された。
また、カーリターダには 英国で開発された「ダウティ式カーリターダ」というものもあり、これはダウティユニットという油圧ダンパーを車輪が踏んだ反発力で貨車を減速するもの。
日本ではこの方式のカーリターダを「自重式カーリターダ」や「油圧式カーリターダ」などとも呼ぶ。ダウティ式には貨車の加速も可能なものも存在した。
ハンプを散転された直後のスピードの速い段階の貨車に対しては、任意の速度制御が可能な空圧式カーリターダを使い、留置車両に連結される直前の減速に簡素な構造の油圧式カーリターダ(ダウティ式)が使われた。
ダウティ式は 日本では高崎操車場で全面的に使われたほか、補助的カーリターダとして、多くの操車場に設置された。
以上の2つのカーリターダーが日本では主役と言えるが、その他にも、海外で実用化されたもので日本でもL6として研究された電磁式リターダ、スクリューの回転で貨車を減速するスクリューリターダ(SR)などもあった。
ハンプから転がってくる個々の散転貨車の重量、速度、風向き風速、温度等を電脳で計算し、カーリターダを自動制御して減速する方式が、1956年(昭和31年)に米国のユニオンパシフィック鉄道で実用化された。
これを「ターゲットシューティング方式」といい、日本のヤード自動化も、まずこれを参考に郡山操車場から始まった。
ただ、坂阜の建設には金が掛かるので、なるべく平面操車場で自動化を図るべく いろいろな装置が開発されてゆく。
適当な速度で転がってきた貨車を、あとから搬送車で捕まえて 加速や減速を自動で考えて速度をコントロールするものを「連続制御方式」という。これには搬送車を使わずに「ダウティ式カーリターダ」で済ませる場合も含まれる。
その後 従来方式リターダーの騒音が問題として、無騒音ゴムリターダーの研究が進められ、内軌条形ロープカーと組み合わせて「GROPシステム」なるものの試験が 東鷲宮の実験側線での行われていたところでヤードが全廃となった。
多岐分岐装置
操車場の貨車仕訳線は1本ないし2本の引上げ線から多数の仕訳線に分岐する構造であるが、これを通常の2線分岐器でやろうとすると広大な用地取得が必要となる。
そこで早くから3線分岐器を導入しているが、昭和50年代初頭には5線以上に分岐するトラバーサー式ポイント等が構想された。
ちなみにヤードでは何としても貨車の滞留時間を減らすため、特にハンプから仕訳線に向かう途中のポイントの高速切り替えが要求されたので、通常の電動モーターではなく、空気圧で瞬時に動く分岐装置が使われていた。
入換用ブレーキ車
平面操車場で貨車の入換速度を向上させたいとき、機関車の加速力・減速力の無さに、なんとももどかしい思いをさせられる。
機関車の加速力の方はいかんともしがたいが、せめて減速だけでも・・・。減速の方はブレーキ軸数を増やせば対処できる。
そんな考えの元、昭和40年、時の仙台鉄道管理局 運転部長によって考案されたのが、入換機関車に専用のブレーキ車を連結するというもの。
最初は廃車のC62形蒸気機関車の炭水車を改造して 長町操車場で9600形に牽かせたところ好結果を得られ、DD13形ディーゼル機関車の導入まで使用された。
ブレーキ車は郡山操車場に転用してDD13との組み合わせで重入換に使おうとしたが、車籍もなく炭水車ではサイズがデカくて見通しが利かないので、今度はミキ1形水槽車を改造。
機関車から直通ブレーキが作用するようにして好結果が得られたらしい。
ただ、DE10形・DE11形の登場により、ブレーキ車は不要となった。
リニアモーター方式貨車加減速装置
戦後進められたヤードの近代化は、主に規模の大きなハンプヤードが対象であり、平面ヤードの近代化は遅れていた。
従来の技術でヤードを近代化・自動化するには 巨額の投資をしてハンプヤード化するしか手段が無く、国鉄は代替手法を模索していた。
欧州ではその頃「可動制動台車方式」と言って ミュール(軌道レール間の走行路を走る装置で車両を押すもの。搬送車。)を使った様々な方式が考案・実用化されていたが、国鉄では開発中の磁気浮上式高速鉄道の技術を 応用できないか考えられるようになった。
リニアならレスポンスが良いので貨車の組成時間を短縮できる。
国鉄が考えた装置はL1~L6まである。
L1カーは、低速で仕訳線に向けて貨車列を押す機関車の役目をおわせるもの。
L2カーは、L1カーから引き継いだ貨車を急加速・急減速して突放し、停車後、貨車の下をくぐって次の解放貨車まで戻る装置。
L4カーは、転がってきた貨車を受け止めて、速度が足りない時は加速して留置車両前に来たら減速して連結させるもの。
L1カー、L2カー、L4カーは軌道内に敷設した走行路をリニアモーターで走る。
L3はリニアコイル方式加減速装置で、レール両脇にリニアモーターの固定子を設置して、そこを通過する貨車の車輪にモーターの回転子の役目をさせて速度制御させようというもの。仕訳線内の低速用。
L5は、電磁式加速装置(電磁式ブースター)、L6は電磁式減速装置(電磁式リターダー)で、どちらもレールに低電圧大電流の電気を流して、磁界の変化で速度制御しようとするもの。1~1.5km/hで仕訳線内の低速用。
この他、大宮貨車区には、トラバーサーへの車両移動用にL1、L2カーの小形版とも言える装置を試験導入していて、これをさらにヤード向けに改良する計画もあった。
また、L4カーの技術を活用してリニアモーターカーにスノープロ―を付けてヤードの除雪をさせるべく、昭和43年(1968年)に旭川工場で試験がされた。
昭和41年度にL2カーとL4カー、L6は鉄道技術研究所内、L3は大井工場で試験がスタートした。
その後、昭和44年(1969年) 富山操車場にL4カーを自動制御化したものと、L6電磁式リターダーを試験設置。
昭和49年(1974年)の塩浜操車場にてL4カーが実用化された。また、L6電磁式リターダーも高崎操車場に一応導入されたようだ。
L1カー、L2カーは入換機関車の代替であるが、機関車遠隔操縦の方に開発がシフトしたこともあって、技術の目途が付いた時点で開発は中止されたようだ。
というわけで、完成したL4カーが、リニアモーター方式貨車加減速装置の代名詞として語り継がれる事となる。
多くの文献に書かれているので詳細は書かないが、要は突放・散転されてきた貨車を捕まえて速すぎれば減速して、遅ければ加速して、所定位置に停車させるものである。
L4リニアは 最終的には、仕訳線方から貨車を掴むプッシャーカー、ブレーキを掛けるブレーキカー、動作を判断するコントロールカー、動力源のモーターカー、進入貨車を検知するデスタンスカーの5台で構成された。さらに冬期は頭に除雪用のスノウプロ―カーが増結された。
この一連のリニアモーターの技術は、その後 リニア地下鉄の開発に結び付くなど、かなり有意義な研究であったようだ。
エンドストッパー(ES)
これはハンプヤードの仕訳線の末端に設置されていて、突放された車両が仕訳線を行き過ぎないように減速させる装置。
当初郡山操車場でテストされたが、すっこ抜けが多発して、使い物にならなかったらしい。
ところが後年、武蔵野操車場、北上操車場、周防富田操車場で実用化している。
ただし、どうにも情報不足の装置で、郡山操車場と武蔵野以降のものが同じ技術のものなのかは不明。
なんせ、構内配線図上の記号が変化しているので、全然別の機械を同じ名称で呼んでいる可能性もある。
武蔵野のものはよくわからないが、北上操車場のものは軌道内側に設置され、ゴムで押えた内軌レールが車輪フランジが当たるようにして、ゴムの弾性を利用して車両を減速するシンプルな構造。
郡山のやつはL6リニアの発展形だったのかも?
昭和53年(1978年)に武蔵野でエンドストッパーが完成したことにより、濃硝酸タンク車の「武蔵野操通過禁止」表記が「純アルミ」表記に変更されている。
カーストッパ(CS)
「エンドストッパーES」が貨車のスピード抑制位しか効果が期待できないのに対して、「カーストッパ(CS)」は力技で貨車を止める装置である。
構造は、軌道レール間に連結器を受ける腕を埋め込んで、必要時に立ち上げて油圧で緩衝して貨車を確実に止めるもの。通常は地面に潜っているが、大雨で冠水すると使用不能になるもよう。
方面別仕訳線の末端や、駅別矢羽根仕訳線の途中に設置された。
スクリューブースタ(SB)/スクリューリターダ(SR)
どちらも構造は同じで、軌道レールの内側にスクリュードラムというスクリュー状のフィンを付けた装置を埋め込み、スクリュードラムを油圧モーターによって回転させることにより、貨車の車輪フランジをフィンで擦って貨車を加速または減速させるもの。同様のものはスイスで実用化されていた。
スクリューブースターは最高速度15km/hまで加速できるが、用途(設置個所)によって設定速度は変わる。
スクリューリターダーについては 従来のダウティ式や空圧式は うるさいので、フィンの角度を変えるなどして低騒音を期待したものだ。
実用化されたのはスクリューブースターだが、入換中は常に回転していて稼働時間が長いので、やっぱり騒音が気になるとの話も残されている。
この装置は、使い方によっては画期的なヤード機械である。
というのも、従来の大規模ヤードは入換時間の短縮を図るために高い丘から高速で貨車を転がして、いかにして減速するかばかり考えていた。
つまり、急加速・急減速で貨車を裁こうとしていたのだが、この急減速の制御が大変であった。あまり急減速すると荷にも悪いし、貨車も強度が必要だし。
周防富田操では考えを変え、スクリューブースタとL4リニアとの組み合わせにより、一定速度で貨車を転がすことを考えた。
狙いは成功し、矢羽根線の転送時隔(貨車を仕訳線に送り出す時間)は、郡山操で60秒、北上操で35秒間隔だったものが、周防富田操では25秒間隔に短縮された。
まあ、機材としては高価だから、大規模ヤードに全導入は困難なんですけど。
カープッシャ(CP)
「カープッシャ(CP)」は平面操車場で機関車の代わりに貨車を突放するための搬送車で、軌道レール間に走行路を設けるのはL2リニアと同じだが、これは油圧モーターで稼働するもの。
北上操車場以降実用化された。
さらに突放以外にも貨車の小移送などにも使うべく、ヤード全廃の時まで改良が続けられていた。
ロープキャリア(RC)
ターゲットシューティング式はともかく、リニアモーター式にしても高い!
ヤードの自動化は遅々として進まず、国鉄ヤード末期に開発が進められたのが「ロープキャリア(RC)」だ。
貨車を搬送する装置(ロープカー)をケーブルで引っ張るもので、構造簡単・価格も安い。荷役施設等で昔からあるものだし、欧州ではヤードで実用化していた。
正式名称は「ロープ式貨車加減速装置」とか「ロープ式貨車搬送装置」で、中小のヤードの自動化に使うつもりだった。
その後、国鉄では分岐器・曲線区間にも対応するように、軌道レール間を搬送車が走る直線用と、搬送車を軌間外に設置した曲線用の2つが作られた。
最初に昭和50年(1975年)に周防富田操車場で実験ののち、昭和53年(1978年)に東鷲宮の実験側線で本格試験が始まった。
簡単な装置のはずなのに、ずいぶんと開発に時間が掛かっているが、なんでだろう?
ちなみに、昭和54年時点では、貨車移動機と共に音声認識でワンマンコントロールする事を目論んでいた。
音声認識でワンマンコントロールする事を目論んでいた。
ともあれ、ケーブルによる車両の移動装置自体は、車両所や工場での車両搬送装置として普及した。
機械式側ブレーキ装置/油圧式側ブレーキ装置
貨車の絵 その1のワム3500形の解説で書いた通り、貨車にある側ブレーキは本来、速度制御に使うものではなく、留置ブレーキである。
極初期には駅に停車中に側ブレーキを利かせ、勾配の抑制ブレーキに使う事も行われたが、走行中には操作しない。
ところが日本では、突放時の速度制御のために使う事を前提に発展してしまった。
側ブレーキの構造は古典の時代には側ブレーキテコの重さでブレーキを利かせていた。
その後、側ブレーキテコ案内にピンを挿入して 任意の位置=任意の制動力 で側ブレーキテコを固定する方法がとられたが、あくまでこれも車両が留まった状態で操作するもの。もちろん貨車に掴まる手摺など無い。
それを貨車に飛び乗って、側ブレーキテコを踏み下げて、片手で手摺を掴んだままもう片手でピンを指す というアクロバティックな行為(元々は現場の発明。)を強制してしまったから、当然、労災の頻度がひどかった。
これではいけないと、少しでも操作を簡略化するため、危険なピン挿し作業をラチェットの操作で済ませるべく、国鉄では昭和25年(1950年)に「ブレーキイージ」という装置を開発。昭和28年(1953年)から全面採用となった。
ブレーキイージーの採用で、側ブレーキの操作はだいぶマシとなったが、そもそも側ブレーキで速度制御自体が危険な行為で、これは最後まで、JR初期に突放入換が禁止されるまで解決されなかった。
まあ、そんな側ブレーキであるが、機械的にも問題があった。
それは、側ブレーキテコをしならせて その反発力で制動力を得るため、一定以上の強いブレーキが利かないのだ。
これでは貨車が大形化していく中で 車両設計に限界が生じる事となる。
補助ブレーキを強くしたいなら 手ブレーキを採用すれば必要なブレーキ力は得られやすいが、時はタキ35000形が量産されていた時代。手ブレーキのあるデッキを廃止して少しでも車体を大きくしたかった。
というわけで、昭和45年度に側ブレーキの効きを強くする研究がされた。「機械式側ブレーキ装置」と「油圧式側ブレーキ装置」である。
どちらも設計コンセプトは似てて、側ブレーキブレーキ軸とブレーキ引棒の間、車体中央にブレーキ比率を変化させる機械を付けたもの。
機械式はテコ比で踏込み力の15.5倍、油圧式は油圧ピストンで踏込み力の34倍の力を発揮する。機器の構造はとっても複雑。
ついでにブレーキ操作自体も少し楽にできるように工夫されていた。
まあ、その後タキ40000形が誕生したように事故対策で貨車にデッキを付けるようになると、こんな面倒なやつより手ブレーキ付けた方が簡単なので、日の目を見なかった。
電気空気管付連結器/貨車連結部自動解放システム(FACS)/貨車連結器自動解放システム/空気ホース解放連結システム
集結貨物列車は、操車場に到着したら まず牽引機関車を解放し、全ての貨車間のエアーホースを切り離す。
しかるのち、入換機関車が連結され、ハンプで行き先別に分解され、同じ方面行の貨車を連結して次の貨物列車が仕立て上げられる。
昭和40年代、カーリターダの普及やL4リニア等の開発の目処が立った事により、次なるヤード自動化は 貨車の自動解放装置の開発であった。
すでに昭和43年(1968年)からセノハチの連結器走行解放のためにコキフ10000とレムフ10000に電気連結器を装備して密着自動連結器のブレーキ管の空気を遮断する事は行われていた。
車両切り離しは機関車側の連結器を解放して行う。
昭和44年(1969年)頃、これを応用し 「電気空気管付連結器」を一般貨車に装備する事が考えられた。
当時考えられていたのは、貨車に電気連結器と 密着自動連結器の解放装置とブレーキ管遮断装置を搭載。機関車から貨車解放指令を出すもの。
解放された貨車はブレーキを掛けて留置か、突放に備えて緩解させるかを選べる。
将来的には編成の任意の貨車間の連結器の自動解放も視野に入れていたようだが、対象貨車は一般貨車であったから、貨車の改造は困難が想像され、研究はお流れになったようだ。
しかし、国鉄の探求は続く。
操車場の貨車取扱能力を向上させるには、ハンプの押し上げ速度を向上する事が必要で、高速押し上げしている貨車の解放テコを人が扱うのは困難が予想された。
昭和40年代中盤には、入換用自動操縦装置の実用化の目処が立ったため、自動解放装置の開発が急がれた。
昭和48年(1973年)頃、機関車からの解放指令方式は諦め、また、連結器の換装もやめて、新たに「貨車連結部自動解放システム(FACS)」が研究された。
これは地上装置から何らかの方法で ハンプ押し上げ作業中の貨車の解放スイッチを動作させて、自動連結器の解放テコを動作させるものである。
空気ホースは新たに自動分離・連結が出来る物を試作し、弁装置の設置など、やはり貨車の改造が必要であったのだが、最低限の改造で装置一式が取り付けられるように考慮されていた。
この装置のキモは貨車に電源を搭載しない事で、各制御は空気圧を利用していた。
地上からの解放指令は、貨車に取り付けた操作弁目掛けて エアーガンで高圧空気を打ち込む エアーガン式解放指令方式と、
軌条間にトランスを設置し、レールに電気を流して車軸をコイル代わりにして電磁弁を動作させるコイル式解放指令方式が実験された。
が、やはり貨車の改造は困難が想像され、研究はお流れになったようだ。
なお 貨車への解放指令は、操車場総合自動化システムの電脳が貨車位置・速度検知装置によって連結順序表を元に計算して、自動で行われる。
昭和40年代後半には、「貨車連結部自動解放システム」と平行して「貨車連結器自動解放システム」も研究された。
これは いたって簡単。貨車の改造は無し。
空気管との同時解放は諦め、自動連結器のみの解放を自動化しようというもの。
ハンプを押し上げられてくる貨車にロボットが並走して、貨車分解のデータに従って指定の貨車の解放テコを ロボットアームが引っかけて解放する。
ロボットは、軌道上に設置された天井クレーンのようなレールに吊り下げられて移動する。
このシステムは 一連の解放システムの本命として 武蔵野操車場への設置を目指していたが、開業に間に合わなかった。
それでも開発は続けられ、最終的な試験は、昭和53年頃 奥羽線 庭坂駅構内にエンドレス走行路式の装置が設置されて行われた。
試験結果は良好との事だが・・・。 しかし、なかなかうまくいかなかったようで、最後は東鷲宮の実験側線での試験が計画されたようだか、その前にヤードが全廃になってしまった。
東鷲宮の実験側線では「空気ホース解放連結システム」の研究もしようとしていたようだ。
これは解結線に貨車組成が留置されている状態で、空気ホースの解放・連結を自動化しようとしたもののようだが、詳細は不明。たぶんこれも貨車の方は改造せず、ロボットアームを走行させて何とかしようとしたのだろう。
機関車自動操縦装置(SLC)
入換作業において、操車担当が運転士を介さずに機関車を直接操縦できたら、両者の意思疎通の不手際による事故を無くせるはずである。
といったわけで、産業鉄道とかでは無線機関車が実用化されているし、低速の貨車移動機(アント等)のリモコン操縦機はJRでも使っている。
戦後の国鉄では ヤード用の大形入換機関車でも これを実現すべく、実験が重ねられた。
そして ディーゼル機関車を遠隔操作する目処は すんなり立った。
しかし国鉄の目標は、入換機関車の遠隔操作から、入換機関車の自動操縦へと変わっていた。
ハンプ押し上げ速度の向上―― 引いてはヤードの貨車取扱能力の増加・貨物の輸送時間縮小が目的である。
ハンプ(坂埠)から散転された貨車の速度を測定して、気象条件とか留置状況を加味してカーリターダーで減速し、転轍器を高速で切り替えて安全に留置貨車に連結する技術は、昭和40年代には いろいろ開発されていたので、あとは どんどん貨車を流してやればよろしい。
そこで、ハンプ押上速度を向上させるためには、上に書いた「貨車連結器自動解放装置」の他に、押上げ機関車の最適な押し上げ速度を実現する必要がある。
今までは先に散転した貨車が分岐器を通過したのを確認して、転轍機を転換。操車が機関士に指示してゆっくり貨車を押し上げていた。
各種センサーでとらえた貨車の情報(貨車の重量とか)を元に「操車場総合自動化システム」の電脳が、最速で最適な押上げ速度を機関車に指令して、自動操縦する。人の手は介さない。
これが武蔵野操車場に導入された無線操縦DE11の本質である。
よく 無線という言葉に惑わされてか、無線操縦DE11は単なるラジコンで、地上で運転士が操縦しているという勘違いされるが、そんなチャチなものでは無いのである。
国鉄では昭和44年(1969年)にはDE10による実験により機関車遠隔操縦の目処を付け、郡山操車場での実用化を考えていたが、実現したのは武蔵野操車場であった。
機関車自動操縦装置(SLC)の自動操縦は 以下の4つの作業に分類され、
まず、着発線に到着した貨車を、ハンプまで持って行く「ハンプ第一押上」。
ハンプから貨車を転送する「ハンプ第二押上」。
ハンプでの作業終了後、待機位置に戻る「機廻り」。
平面ヤードでの「突放」。
であり、実際にDE11形1030、1031、1035、1046号機に その機能が搭載された。
しかし武蔵野で実際に使われた機能は第一押上、第二押上だけであり、運転側の反対で常時機関士が乗務。機廻りは機関士が運転し、危険な時はブレーキを掛ける。
また、留置車両への自動連結は実現しなかったので、結局 機関士が必要なのだった。
で、武蔵野操車場で4両が実戦配備されたものの、後発の北上操車場においては導入されなかった。降雪の際の散転貨車の走行抵抗を考慮したのかもしれない。しかし。
そもそも、ハンプ高速押上げには 先に書いた貨車の連結器自動解放の実用化が必要で、機関車自動操縦装置だけを導入しても、意味が無かったのであった。
車号読み取り装置
貨物列車が走る時は、情報も走る。
その情報とは、「この列車には どんな貨車が どんな順序で連結されていて、それぞれの積荷はなんで、どこまで、いつまでに行くのか?」という情報である。
それらの情報は発駅から連結順序表として電報で次駅に送られる。
この貨車の連結順序を管理するのは配車の仕事であるが、むかしは列車が到着したり組成されるたびに、歩いて貨車の車号と車票を記録して廻っていた。
そして その速記されたものを電報で打つ。当然 時々間違いがあるから、着駅でもまた確認する。
貨車の積荷とか行き先は 主に営業上のデータで、徐々にネットワーク化が進められたが、実際の貨車の動きを知るには、貨車の車号を目で見て記録する作業が残った。
これを自動化しようと、昭和40年代に光学式自動番号読取装置が実験された。
これは貨車にコード表を張りつけて、それをカメラで記録して電脳が読み取るもの。
そしてそのデータは、誤記される事無く 各所に送られる。
なぜコード表を使ったかというと、複雑な形の貨車の、どこに書かれているか分からないナンバーを、電脳が探しだして間違いなく読み取るのは、当時の技術では不可能だったから。
光学式自動番号読取装置は 北海道において ある程度の規模で実験されたが、コード表が汚れると読み取れなくなるなど 当時の技術では実用化困難であった。
しかし、昭和49年(1974年)に開業の武蔵野操車場では、貨車や機関車の車号を直接読み取る「ナンバー自動読取装置」が導入されたという。
コード表を使わず、ただ機関車のニッケルメッキの車号は読み取りにくいから白でペイントしたのだが、当時の技術としては すごい進歩である。
実際のシステムとしては、カメラで記録するところまでは、北海道の実験と同じ。
凄いのは、テレビのモニターを注視した担当者が、ナンバーを読みとって・・・・・・?
・・・一応 自動読取装置も試験していたようですが、信頼性が乏しく、結局人手がいるのでした。
多数の貨車が往来する 危険な駅構内を歩きまわる作業を しなくて済むようになったのは大きな進歩?です。
貨車偏積測定装置/貨車到着自動検査システム(FIIS-C)
鉄道車両は各車輪に掛かる重量=輪重がアンバランスだと、容易に脱線する。
特に貨車の場合、積空差はもちろん 積荷の偏り具合によって輪重は常に変動するので、国鉄では昭和26年(1951年)から鉄道技術研究所で「貨車偏積測定装置」の研究が開始され、昭和31年(1956年)に開発完了。
検測装置は軌道に埋め込まれていて、ここを到着列車が20km/h以下で走行する事により測定する。手始めに、新鶴見操車場、稲沢操車場、吹田操車場に設置された。
昭和39年(1964年)には測定数値異常の車両の軸箱に着色グリスを吹き付けて マーキングできるようになるなど、順次機能向上が図られ、設置個所は10ヶ所に増加した。
武蔵野操車場の開業に当たっては、いわゆる操車係が駅構内に出ないでも済むように考えられていたが、貨車の検査をする要員は必要であった。
車両の検査は現物を見ないと行えない。
ともあれ、自動化できる作業は無人化しようと、「貨車偏積測定装置」を発展させたものが「貨車到着自動検査システム(FIIS-C)」だ。」
昭和49年(1974年)の開業時点では とりあえず、偏積と過積載の検知の他に、軸箱の過熱も検知できるようにした。通過速度も45km/hまで対応した。
さらに昭和55年(1980年)の時点では、車輪の割損や異常振動も検知できるようになった。
装置の改良は続き、これら装置は現代もJRで運用されている。
ヤックス
YACS、操車場総合自動化システム
機械なり装置なりを 自動化・無人化するためには、まず、多数のセンサー(情報)が必要である。
大昔のSFで絵描かれるロボットが鉄骨むき出しだったのに対し、今のそれは より生物的外見をしているのは、その辺が一般常識化したから。
そしてその情報を反射的、直感的、客観的に処理するための神経が必要で、それはいわゆる電脳よりも重要だ。
話がそれたが、
武蔵野操車場
昭和40年代、なぜ国鉄で自動化・省力化が重視されたかというと、労使問題が大きい。加えて操車場の場合は、労災事故も深刻な問題であった。
しかし、武蔵野操車場が計画された頃には 状況が変化し、「人の物理的限界を超えた操車能力」を目指すようになった。
建て前は、貨物駅を拠点駅に集約したら 貨車がそこに集中して、既存のシステムではパンクすると考えて「人→機械化」を図ったという。
でも、残された資料を見ると、あの頃の雰囲気は「来たる21世紀の夢の世界」を、まさしく「夢見て」いたように感じてならない。武蔵野操車場は入換作業の完全無人化を目指していた。
当時は「省力化」名目なら すんなり予算も現場の協力も得られたようだ。夢の実現にためには・・・。
武蔵野操車場は夢の操車場。
しかし無人化のための各要素の開発は難航し、この頃色々開発されていた各システムを全て組み合わせて やっと正規の能力を発揮するはずの武蔵野操車場は、未完成のまま失敗作に終わった。
未熟な武蔵野操車場は、多量に押し寄せる貨車を捌ききる事が出来ず、ヤックスはダウンした。
しかも その押し寄せる貨車とは、駅に置く場所が無いから とりあえず列車に連結して本線上を走らせていた 貨物を積んでない空車ばかりだったのである。
クレーンによるコンテナ荷役と、フレートターミナル情報システム(FIS)
日本では昭和34年(1959年)に5tコンテナ(総重量6.3t)が導入されたが、その荷役に活躍した機械は、既製品の10tフォークリフトであった。
当時は諸外国でもコンテナ輸送は発展途上で、荷役方式も色々試されたが、一般的にはクレーンによる荷役に進んでいた。
なぜかと言えば、大きな貨物駅には大抵重量物荷役のためのクレーンが備わっていたからで、それを活用したためだ。
また、フォークリフトの場合は旋回スペースが余分に必要な事もあり、国鉄の本命も橋形クレーンであったようだ。
ただ、クレーンの建設には多額の初期投資が必要なため、主にコンテナ取扱個数が多い拠点駅に コンテナ専用橋形クレーンを整備することにした。
また、コンテナの取り扱いは そこそこあるもののクレーンの投資に見合わない駅には、5tコンテナ用7tフォークリフトを開発することにし、その他、コンテナ取扱個数が少ない駅には一般貨物・コンテナ供用クレーンや、回転フォークリフト、フォーク自動車、一般貨物兼用自動車クレーンを開発。さらには新幹線貨物輸送計画の一環のペンジュラム式(シフター式)水平荷役装置や、配達先構内での荷役も視野に入れたコンテナ移載自動車、台車式コンテナ移載機が研究・試運用されていた。
さて、最初に登場したコンテナ荷役用クレーンは、やはり一般重量貨物と兼用できるもので、すでに昭和36年(1961年)には かたちとなっている。
具体的にはクレーンのフックの先に取り付ける“コの字”形状のアタッチメントで、上を吊って下のフォークで コンテナをすくい上げる構造のものだ。
なお、別にアタッチメントが無くても 通常のクレーンでもコンテナの荷役は可能だが、ワイヤー掛けが面倒である。
国鉄のコンテナ荷役の本命であるコンテナ荷役用橋形クレーンは、昭和40年代初めに 横浜の高島駅に試作機とおぼしきものが登場した。
構造は下吊り式だが、特徴はヤグラ(コラム)が そそり立つ ポスト式昇降装置を採用した事で、これにより上下方向の昇降を安定させると共に、コンテナ水平旋回装置を装備した。
ワイヤーでただ吊っただけだとブラブラし、貨車やトラックに載せるのにコンテナを支える人が必要なので、その対策である。
昭和44年(1969年)には神戸港駅に海上コンテナ用橋形クレーンが導入された。
こちらは4本のワイヤーでスプレッダという上吊り枠を吊りあげる方式で、コンテナの水平旋回は出来なかったものの、既に諸外国で一般的な構造のコンテナ用橋形クレーンであった。
国鉄でも さっさとこのタイプのクレーンを各地に配備すべきであった。
だが、国鉄は自動化・省力化の迷宮に突入する。
コンテナの取扱個数は年々順調に増加しており、国鉄は それが今後も増えつづけると思っていた(※オイルショックでは燃料高騰で、逆にトラックから鉄道に貨物が転移するとさえ思っていた。)。コンテナ列車コキ車30両編成化が必要になると考えた。そして、多量のコンテナの取扱いを 全部人手でやるのは限界があると判断し、だったら最近流行りのコンピュータでコンテナ荷役を全自動化した方が良い。いや、できると妄想したのだ。
コンテナを自動荷役するには、移載機とコンベアを組み合わせた 現代で言うところの自動化倉庫のようなものも夢想されたが、現実的にクレーンによる事にした。
ただ、 やはり吊り上げたコンテナを安定させる必要があり、高島駅の試作機同様 ポスト式を採用する事とし、吊り枠は上吊りスプレッダに変更した。
このため、コンテナも上吊りに対応するC21形コンテナを先行増備した。
クレーンの機構的には こんなもんで良く、昭和49年(1974年)に東京貨物ターミナル駅に1レーン(荷役線2本コンテナ留置場所2列トラック1列)に5機が試験導入された。
このクレーンは20ftコンテナにも対応し、扱い荷重は12.3t。
問題は自動化の部分である。
これはフレートターミナル情報システム(FIS)の一部分を構成する。
フレートターミナル情報システムを簡単に説明すると、
① トラックがコンテナを運んで貨物駅に入ってくる。
② 駅の受付でコンピューターに入力すると、トラックの行き先が指示される。
③ トラックが指定された場所に着くと、クレーンが勝手にコンテナを掴んで、貨車に積む。
といふもの。
貨車の方ではコキ9300形(貨車の絵 その5を 参照。)でコンテナ自動緊締装置が試作されたが、こちらは早々に諦め、作業員が人力で行う事とした。
トラックのコンテナ緊締もそうである。
コンテナがちゃんと安全に積まれているかの検査も、人力。
「クレーンが勝手にコンテナを掴んで、貨車に積む。」が曲者であった。
クレーン・貨車・トラック・コンテナの位置・向き等をセンサーで正確に捉えなくてはならない。
作業指示とか そっちの電脳系は なんとかなったが、このメカとコンピューターが絡む所は 現代でも なかなか難しいであろう。
東京タに試験設置された時点では、クレーンの上下昇降の自動化は後日開発となっていた。
ばく大な お金を掛けて せっせと開発して、昭和52年(1977年)には クレーンの方は一応完成した事にしたが・・・。
国鉄末期?JR初頭?
一連の施設は、いつの間にか撤去されていた。
同じお金で、どれだけの貨物駅に普通の橋形クレーンを配備する事ができたであろうか。
そうすれば、どれだけのフォークリフトの運転操作誤りによる荷痛みを無くして、荷主に悲しい思いをさせる事を防ぐ事が できたであろうか。
コンテナバイパス輸送計画
昭和40年代中盤の国鉄は、従来の車扱い輸送に替わりコンテナ輸送が伸び続ける↑と本気で考えていた。
車両の方はコンテナ車などの増備で対処しようとしたが、問題は輸送力の方で、具体的には青函連絡船の航送輸送がボトルネックとなると恐れられていた。
そこで、コンテナという輸送容器の特性を生かして、東京港~室蘭港にコンテナ船航路を開設しようと検討された。
コンテナ船は5tコンテナ300個積を想定したが、問題は船への荷役時間で、それも絡んで上述のガントリークレーンも研究されていて、この場合、5tコンテナを一度に数個掴んで荷役する方法(海上コンテナで実績あり。)を取り入れようとしていた。
まあ、このコンテナバイパス輸送計画は、すぐに立ち消えになったんだけどね。
手小荷物自動処理システム
昭和54年(1979年)に開業の横浜羽沢駅に導入されたもの。稼働年数7年。積荷の絵その1のロールボックスパレットの解説を 参照。
ちなみに横浜羽沢駅の荷物扱い個数1日平均16000個のつもりで これを使用開始して、昭和58年(1983年)の年末ピーク時の荷物扱い実績は、1日2500個。
どう考えても手仕訳の方が効率が良いのに、構内レイアウトの都合でシステムを通さざるを得なかったとの事。
スライドバン
フレキシバン
ピギーバック
国鉄がボキシーバック(=コンテナ)と共に昭和30年代から実現を夢見た輸送方式。
貨車の絵 その11のクム80000形、クム1000系、クサ1000形の解説を 参照。石油ピギーバック輸送については、貨車の絵 その9のクキ1000形の解説を参照。
石油パイプライン
昭和40年代初め、国内の石油需要の増加は留まる事を知らず、毎年10%という底無しの急激な伸びを示していた。
それに応えるため石油元売り各社は各地に石油備蓄基地を開設、ちょっとした内陸駅にはその専用側線が増えていった。
ただ、国鉄としては各駅での入換作業が煩雑になり、コストも増加するため日本オイルターミナルを設立。内陸部に拠点石油備蓄基地を建設し、石油列車の直行輸送化、タキ43000系による貨車の大形化で輸送需要の増加に対処した。
それと並行して考えられたのが石油パイプラインの建設である。
具体的には、沿岸の製油所から内陸の備蓄拠点まで鉄道線路敷地内にパイプラインの敷設を想定した。当初は横浜~八王子間を計画したようだ。
国鉄が目指したパイプラインは原油用ではなく、末端消費用の各種白油が混在するもので、これをガソリン→灯油→軽油→灯油→ガソリンのサイクルで連続輸送するもの。
複数油種を連続送油するには、油種切換時の混合油(コンタミ)やオイルハンマ(流速急変に伴う衝撃波)等の研究がキモで、まず、とうに実用化していた米国のパイプラインを視察・研究し、昭和46年(1971年)には 鉄道技術研究所内に実証実験用パイプラインを敷設した。
研究は順調に進み、同年には建設の大臣認可まで下り、川崎~南埼玉 間110kmを着工する寸前となった。
が、なんやかんやで国鉄内外でゴタゴタがあったようで、遅延に遅延を重ね、昭和49年(1974年)の第一次オイルショックに突入してしまったのであった。
なお、石油パイプラインの研究は無駄にはならなかったようで、単一油種(JetA-1用とJetB用の2本を併設。)ではあるものの、成田空港の航空燃料パイプラインで生かされている。
真空チューブ輸送
新貨物輸送方式とも言われ、
新専貨
昭和59年(1984年)2月、ついに国鉄は集結輸送方式に見切りをつけ、全国の操車場を一斉に廃止した。世界の鉄道史上、画期的な英断である。
この改革により貨車が5割以上減の40000両に、機関車が3割近く減の1700両に削減され、ワラ1形等のいわゆる黒貨車の多くが廃車。貨物取扱駅も逐次減少し、私有貨車や収入を貨物輸送に頼っていた地方鉄道は大打撃を受けた。
ところが、この改革はまだ道半ばであり、各企業がタンク車やホッパ車でおこなっていた化成品等の小規模車扱い輸送は、国鉄だけの都合で急にやめるわけにいかず、存続させなければならなかった。また、それら企業の専用線が多数存在する臨海鉄道にとっても死活問題で、その輸送の維持が求められた。
そこで考えられたのが「新専貨」という方式で、ヤード(操車場)が行っていた方面別入換作業を、臨海鉄道の駅で代行することとし、収入源とするとともに、化成品等の輸送を存続させることとした。
こうすれば、国鉄(JR)は各臨海鉄道間を結ぶ疑似直行列車(新専貨)を運転すれば良く、駅での入換作業も削減する事が可能となった。
貨車ファンの最後の拠り所とも思われたこの新専貨方式も、順次トラック化や化成品コンテナ化が進み、私有貨車も廃車が進行、平成21年(2009年)に事実上全廃された。
代わりに現代は各種コンテナが花盛りで、かつての貨車ファンはコンテナファンとなり、バラエティ豊かなコンテナを追うのに余念が無いようである。
国鉄時代に考えられたヤード・コンテナ・手小荷物関係の各種機械化、新構想の輸送方式等は、失敗作も多く、結果的に浪費ばかりが目立つ。
しかし国鉄全体でみると、得られた経験を活用して 旅客サービスのシステム開発に応用したり、技術が意外と有効利用されている。
そしてそれは国鉄にとどまらず、開発に参加した民間企業の技術・経験向上に役立っており、日本の国力の底上げにも寄与していたのだ!!
・・・でも・・・無駄遣いし過ぎたよね・・・。
表紙へ




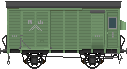
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
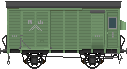
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
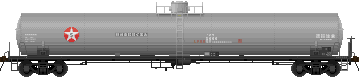
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
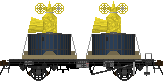
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
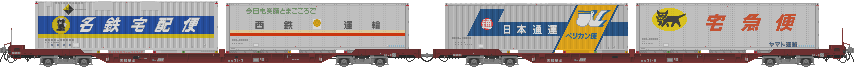
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
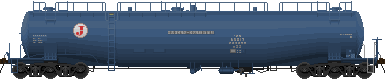
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()